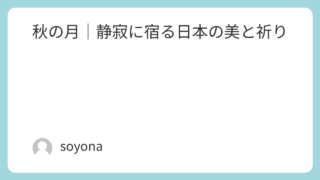 四季をめぐる花と日本の心
四季をめぐる花と日本の心 秋の月|静寂に宿る日本の美と祈り
秋の夜、静かな空に浮かぶ一輪の月。その光を見上げるとき、人の心はふと穏やかになります。月は、ただ明るいだけの存在ではなく、“時間”や“心”の奥にある静けさを映す鏡のようなもの。古くから日本人は、秋の月を愛で、詩に詠み、その光に思索や祈りを重...
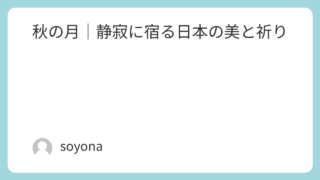 四季をめぐる花と日本の心
四季をめぐる花と日本の心 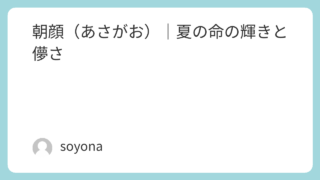 四季をめぐる花と日本の心
四季をめぐる花と日本の心 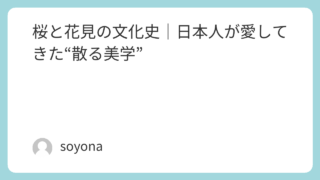 四季をめぐる花と日本の心
四季をめぐる花と日本の心 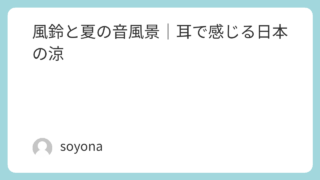 四季をめぐる花と日本の心
四季をめぐる花と日本の心 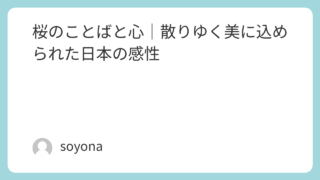 四季をめぐる花と日本の心
四季をめぐる花と日本の心 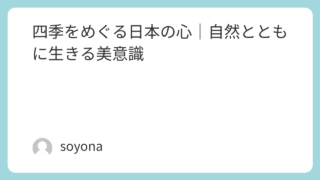 四季をめぐる花と日本の心
四季をめぐる花と日本の心 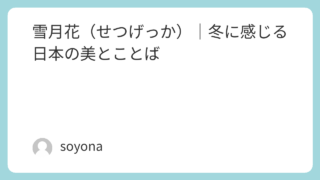 四季をめぐる花と日本の心
四季をめぐる花と日本の心 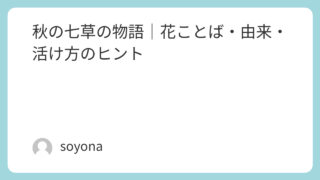 四季をめぐる花と日本の心
四季をめぐる花と日本の心 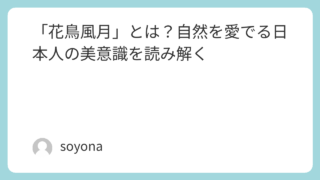 四季をめぐる花と日本の心
四季をめぐる花と日本の心 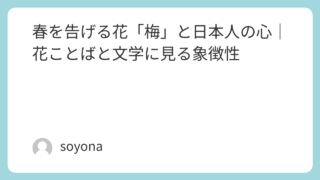 四季をめぐる花と日本の心
四季をめぐる花と日本の心