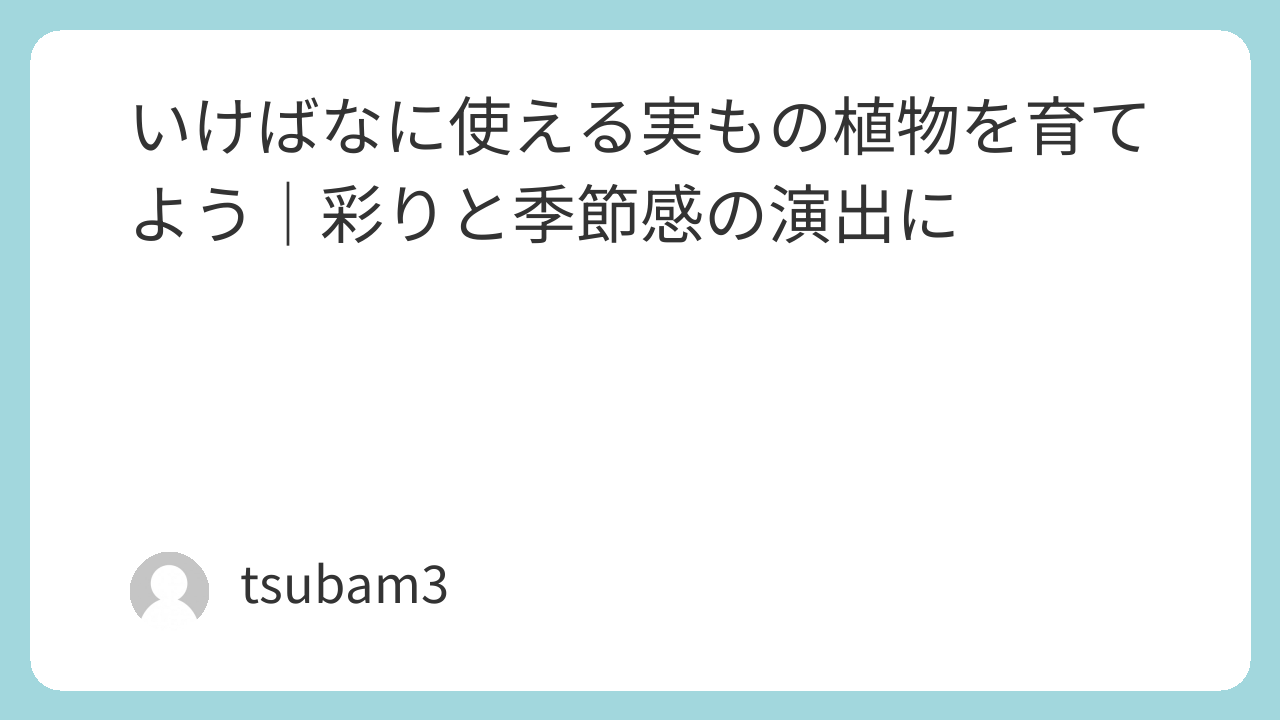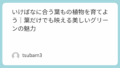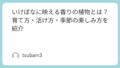はじめに|いけばなに活かせる「実もの植物」とは?
実がなる植物(=実もの植物)は、いけばなに季節感や奥行きを与えてくれる大切な花材です。
とくに秋から冬にかけては、赤く色づいた実や葉を落とした枝に宿る静けさが、作品に深みを添えてくれます。
本記事では、初心者でも育てやすく、剪定・活用もしやすい実もの植物を7種ピックアップ。
育て方、いけばなでの活用法、剪定カレンダー、季節別の演出法などをわかりやすく紹介します。
実もの植物とは?|いけばなにおける役割と魅力
実もの植物とは、読んで字のごとく「実をつける植物」のこと。いけばなでは、花材の一種として扱われ、特に以下のような魅力があります。
-
色味で季節感を伝える(例:赤や紫の実は秋・冬を象徴)
-
花よりも持ちが良く、長く楽しめる
-
枝ものとしての力強さと実の可愛らしさの対比
-
「実を結ぶ」ことの象徴的意味(縁起物、祝事にも)
実は、開花時期よりも長く鑑賞できることが多く、花が乏しい季節に重宝されます。また、色や形によりさまざまな表現が可能で、シンプルな一枝でも十分に作品として成立することが特徴です。
育てやすい実もの植物7選(家庭向き)
初心者でも育てやすく、剪定や管理が比較的しやすい「いけばな向けの実もの植物」をご紹介します。庭植え・鉢植えの両方に対応している種類も多く、育てながら活けられるのが嬉しいポイントです。
| 植物名 | 見頃の季節 | 実の色・特徴 | 栽培のポイント | 活け方・特徴アイコン |
|---|---|---|---|---|
| ヒメリンゴ | 秋 | 赤く小さい実が鈴なり | 鉢でも育てやすく、✂剪定しやすい | ◎初心者向け/✂剪定しやすい |
| ナンテン | 冬 | 赤く房になる実 | 半日陰でも育ち、病害虫に強い | ◎初心者向け/☀半日陰OK/🔴縁起物 |
| ムラサキシキブ | 秋 | 紫の細かい実が美しい | 自然樹形で整い、✂剪定も容易 | ✂剪定ラク/🍇紫実が美しい |
| フユイチゴ | 晩秋~冬 | 食べられる赤い実 | グランドカバーとしても使える | 🌱地面を這う/🍓食べられる実 |
| クロガネモチ | 冬 | 鮮やかな赤い実 | 常緑で目隠しにも/大きく育つ | 🌳常緑/🔴縁起物/📏中~高木 |
| ユスラウメ | 初夏 | 透明感ある赤い実 | 小庭でも育てやすい低木 | ◎初心者向け/🍒観賞+収穫両用 |
| グミ類(ナツグミ・アキグミ) | 初夏~夏 | 銀がかった渋い実 | 丈夫で形も整えやすい | 🌿強健/🍃涼感表現に◎ |
| アイコン | 意味 |
|---|---|
| ◎ | 初心者におすすめ |
| ✂ | 剪定がしやすい/管理が簡単 |
| ☀ | 日当たり条件(半日陰でも可) |
| 🔴 | 縁起物としての利用価値あり |
| 🍇🍒🍓 | 実が観賞用または食用になる |
| 🌿🌱🌳 | 成長特性(地を這う、丈夫、高木など) |
| 📏 | 樹高に注意が必要な植物 |
これらは見た目の美しさはもちろん、管理のしやすさ、いけばなとの相性も良好です。1~2年で実が楽しめるものもあり、育てる喜びと活ける楽しさの両方が味わえます。
季節別に楽しむ実ものの魅力
実ものは、一年を通して表情が変わります。季節ごとの楽しみ方を知っておくと、いけばなにも自然な移ろいが生まれます。
-
春:まだ青い実や花と実が混在する時期。希望や生命力を表現。
-
夏:グミ類など初夏の実が涼やか。青みがかった実が清涼感を添える。
-
秋:赤・紫・オレンジの成熟した実が登場。深まる季節を象徴。
-
冬:葉が落ちた枝に残る実の静寂さ。余白の美や余韻を表現。
実の「色づき」は、単に美しいだけでなく、成熟・熟成といった意味合いを作品に与えます。特に和の空間や床の間などでは、派手さを抑えた実ものの取り合わせが好まれることもあります。
実ものをいけばなに活かすコツ
実ものは、取り扱い方次第で作品の印象が大きく変わります。以下のポイントを意識して活けてみましょう。
-
実が落ちにくいタイミングで剪定する
実が熟しすぎると落ちやすくなるため、色づき始めの頃が理想です。 -
葉と実のバランスを調整する
葉を一部取り除くことで、実の存在感を強調できます。 -
他の花材との色合わせ
赤い実には白系の花、紫の実には緑や黄色がよく合います。 -
枝のラインを活かす
実ものは枝ぶりも作品の魅力の一部。剪定前に構成を考えておくと◎。
育てて楽しむ+活けて楽しむ|家庭菜園とのハイブリッド提案
いけばなを嗜む人にとって、「育てて活ける」という体験はとても充実感があります。
例えば、庭やベランダに実もの植物を植えておき、季節ごとに剪定しながら花材として活用する。
日常の手入れが、やがて一枝の作品になる――そんな暮らし方も可能です。
とくに鉢植えで管理できるヒメリンゴやユスラウメ、ナンテンなどは、限られたスペースでも育てやすく、花材としても長く使えるためおすすめです。
失敗しないための育て方Q&A
Q. 実がつかないのはなぜ?
A.日照不足、剪定の時期が悪い、樹勢が強すぎるなどが原因。花が咲いたかどうかも確認しましょう。
Q. 剪定はいつ行えばよい?
A. 花後~初夏にかけての時期が適しています。翌年の花芽を切らないよう注意。
Q. 害虫対策は必要?
A. 実ものにはアブラムシがつきやすい傾向があります。葉裏のチェックを定期的に行い、自然由来の防虫剤などを使用しましょう。
Q. 鉢植えの場合、どのくらいのサイズが良い?
A. 5〜10号鉢を目安に。地植えが難しい場合は、根の張りを考慮して徐々に鉢を大きくしましょう。
実もののある暮らし|日常での取り入れ方アイデア
いけばなだけでなく、実もの植物は日々の暮らしの中でも楽しむことができます。
-
玄関に一枝
季節を感じさせる枝ものは、来客にも好印象を与えます。 -
リースやスワッグに
ドライにしても色が残る実は、長く飾れるインテリアにもぴったり。 -
収穫して食べる楽しみ
フユイチゴやグミなど、食べられる実なら収穫の楽しみも加わります。
植物と共にある暮らしの中で、実ものは視覚・味覚・感性すべてに訴えかけてくれる存在です。
実もの図鑑|いけばなで映える20種リスト
※以下は、育てやすさ・鑑賞性・いけばなでの活用度をもとに選んだ実もの植物の代表例です。
いけばなに取り入れやすく、育てる楽しみもある実もの植物を20種類ご紹介します。色・形・実の付き方など個性豊かな実ものを、一覧で眺めてみましょう。
| 植物名 | 見頃の季節 | 実の色・特徴 | 栽培の特徴 | いけばなでの活用法 |
|---|---|---|---|---|
| ヒメリンゴ | 秋 | 小さな赤い実 | 鉢植えも可能で育てやすい | 細い枝を活かした単体使いに |
| ナンテン | 冬 | 房状の赤い実 | 縁起物として定番 | 正月花材として人気 |
| ムラサキシキブ | 秋 | 細かく連なる紫の実 | 自然な樹形で剪定も簡単 | 線の美を活かす生け方に |
| サンキライ | 晩秋〜冬 | 緑→赤へ色づく実 | ツル性でドライにも◎ | リースや動きのある演出に |
| クロガネモチ | 冬 | 丸く鮮やかな赤い実 | 常緑で剪定耐性あり | 大型作品にアクセントを |
| ユスラウメ | 初夏 | 透明感のある赤い実 | コンパクトな低木 | 和の小作品にも好相性 |
| グミ類(ナツグミ・アキグミ) | 初夏〜夏 | 銀~赤の渋い実 | 丈夫で成長が早い | 涼しげな表現に向く |
| フユイチゴ | 冬 | 赤く熟す食用の実 | 地面を這うように育つ | 地を流す構成や実取りに |
| ヒペリカム | 秋 | 赤・ピンク・緑の実 | 鉢植えでも育つ | 洋風ブーケとの相性良好 |
| ノイバラ | 秋〜冬 | 小さい赤い実 | トゲあり、自然風で育つ | 野趣を添えるアクセントに |
| ハナミズキ | 秋 | 枝と実が同時に目立つ | 落葉高木で樹形も美しい | 秋の主枝として使える |
| イチイ(オンコ) | 晩秋〜冬 | 赤い実と針葉が特徴 | 常緑で剪定対応 | 和室向けの落ち着いた演出に |
| ピラカンサ | 晩秋〜冬 | 赤・橙・黄の実 | 実が多くつきやすい | 鮮やかな実を作品に活用 |
| ハクサンボク | 秋〜冬 | 赤から黒に変化する実 | 樹形も美しく成長 | 色変化を作品に取り入れる |
| ゴンズイ | 秋 | 赤×黒の2色実 | 個性的、庭木にも | 珍しい花材として人気 |
| ツルウメモドキ | 秋 | 黄→赤に変化、殻が弾ける | ツル性で管理に注意 | 動きと色変化の両方に対応 |
| ヤブコウジ | 冬 | 常緑で赤い実 | 低木で地表に近い | 草ものと好相性 |
| センダン | 秋〜冬 | 紫褐色の実 | 高木、実が落ちにくい | ドライ利用にも適す |
| ナワシログミ | 晩春〜初夏 | 銀→赤の渋い実 | 銀葉との組み合わせも◎ | 涼しさ・渋さを演出 |
| ヤブムラサキ | 秋 | 紫色の細かな実 | ムラサキシキブに類似、強健 | 庭木としても活用しやすい |
🌿実もの図鑑の使い方ヒント
-
ナチュラル感を出したい時:ノイバラ・サンキライ・ムラサキシキブ
-
お正月や慶事向き:ナンテン・クロガネモチ・ヒメリンゴ
-
洋風アレンジにも使える:ヒペリカム・ピラカンサ
-
夏の涼感表現に:グミ・ナワシログミ・ユスラウメ
実もの植物の“剪定&収穫”カレンダー|いけばなに活かす手入れの年間計画
実もの植物は、正しいタイミングで手入れや剪定をすることで、美しい枝ぶりや豊かな実付きが得られます。
ここでは、**代表的な実もの植物を中心に、いけばな向けの「剪定・収穫カレンダー」**を月ごとにご紹介します。
| 月 | 主な作業内容 | 対象植物の例 | 補足ポイント |
|---|---|---|---|
| 1月 | 冬剪定・寒肥 | ナンテン、クロガネモチ | 枝ぶりを整える剪定はこの時期が適期。株元に寒肥も◎ |
| 2月 | 剪定・植え替え準備 | サンキライ、ムラサキシキブ | 萌芽前にツルや枝を軽く剪定。鉢植えは植え替え準備を |
| 3月 | 発芽前の整枝 | ヒメリンゴ、ユスラウメ | 花芽を傷つけないよう注意しながら整枝 |
| 4月 | 開花時期の観察 | グミ類、ユスラウメ | 花と葉の状態を確認。必要に応じて軽剪定 |
| 5月 | 開花後の剪定(お礼剪定) | ユスラウメ、ヒペリカム | 実付き促進のため、花後すぐの剪定が効果的 |
| 6月 | 摘果・枝整理 | グミ類、ヒメリンゴ | 実が多すぎる場合は摘果を。枝の混み合いも整理 |
| 7月 | 害虫対策・水管理 | ナツグミ、ピラカンサ | 害虫(アブラムシ・ハマキムシ)に注意。葉裏を観察 |
| 8月 | 夏越し管理・水やり徹底 | ムラサキシキブ、ユスラウメ | 暑さで実が落ちやすくなるため日陰管理・水やり強化 |
| 9月 | 実の色づき観察・剪定控えめ | ハナミズキ、サンキライ | 実の色づき始めは剪定を控えて観察を楽しむ |
| 10月 | 収穫・いけばな利用スタート | ヒメリンゴ、ムラサキシキブ | 実のハリや色が美しい時期。剪定を兼ねて収穫を |
| 11月 | 実もの剪定・枝取り | ナンテン、ツルウメモドキ | いけばなに使える良い枝を選んで剪定 |
| 12月 | 正月用花材の準備・整枝 | ナンテン、クロガネモチ | お正月飾り用に最も活躍。剪定とともに枝を確保 |
📌いけばな向けのポイントまとめ
-
剪定と収穫を同時に行うと効率的で、樹形の管理と花材収集が両立できます。
-
色づき始めの“ハリ”がある時期がベストな収穫タイミング。熟しすぎると実が落ちやすくなります。
-
花芽を誤って切らないよう、夏以降の強剪定は避けるのが安全です。
🌿補足:剪定におすすめの基本道具
-
剪定バサミ(細枝用と太枝用の2種)
-
グローブ(トゲあり植物対策)
-
収穫バスケット・剪定くず用の袋
-
ハサミ消毒用のアルコールスプレー
ミニエッセイ|“実”に込められた文化と意味
小さな実には、大きな意味が込められています。
秋に赤く色づくナンテンの実を見て、「もうすぐ年末だな」と季節の移ろいを感じたことはありませんか?
冬枯れの庭にぽつりと残る実、枝の先で風に揺れる小さな赤い粒。
そんな光景のなかに、日本人は昔から「豊かさ」や「希望」、ときに「厄除け」の意味を見出してきました。
たとえばナンテン(南天)は、「難を転ずる」という語呂合わせから、魔除けや縁起物として親しまれてきた植物です。
正月飾りに欠かせないだけでなく、家の玄関や鬼門に植えられることもあります。
実を結ぶということは、「物事が実を結ぶ」「努力が報われる」ことの象徴でもあり、祝いの席でも重宝されてきました。
また、いけばなでは「実」は単なる装飾ではなく、時間の流れを表現するものとして使われます。
花が咲く前のつぼみ、咲いた後の実、落ちた後の枝――それぞれが季節と命の循環を語ってくれるのです。
海外でも、実はさまざまな象徴として用いられています。
たとえばヨーロッパでは、クリスマスの飾りに使われるヒイラギの赤い実には「キリストの血」を象徴する意味があり、緑の葉は永遠の命の象徴とされています。
また、ブドウの実は古代ローマ時代から「豊穣」や「祝福」の印として祭礼に用いられてきました。
つまり、実もの植物とは、**文化を映す“小さな鏡”**のような存在。
それをいけばなで使うということは、ただ美しさを飾るのではなく、言葉にならない物語や願いを、枝の先に託すことでもあるのです。
日々の中でふと実のなる枝を見つけたとき、その向こうにある誰かの祈りや季節の気配を思い出してみてください。
いけばなは、その一枝に、目には見えない「意味」を活ける芸術でもあるのです。
まとめ|実もの植物を通じて、四季を暮らしに取り入れる
実もの植物は、花に比べて控えめながらも、確かな存在感と四季の移ろいを感じさせてくれる花材です。
育てる手間の中に喜びがあり、活ける瞬間に静かな感動がある。
もし「花材がマンネリ化している」「季節感をもっと大事にしたい」と感じているなら、ぜひ実もの植物を育ててみてください。
花ではなく、静かに季節を伝える実の姿。その静けさに耳を傾けることで、いけばなも、暮らしも、少しずつ豊かになっていきます。
このテーマに興味がある方へ
– [いけばなに使える「多年草・宿根草」を育ててみよう|毎年楽しめる花材たち]
– [いけばなに映える「花のない植物」たち|葉・枝・実で魅せるアレンジ術]
– [日本の四季といけばな植物|季節ごとの「意味」を楽しむ]