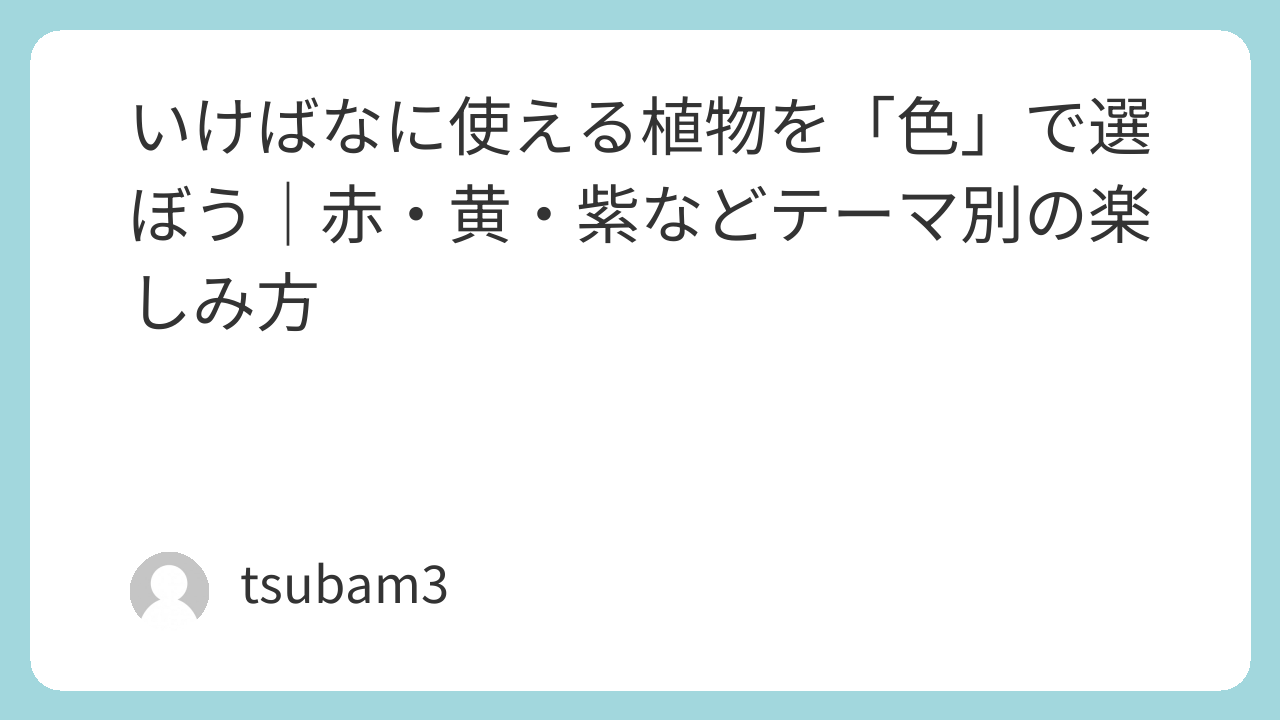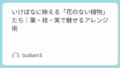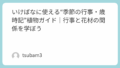はじめに|「色」から始めるいけばな
いけばなを続けていると、作品の印象を大きく左右する「色」の力に気づくようになります。
赤、黄、紫、白、緑……同じ花器や構成でも、使う色によって雰囲気はまったく異なり、見る人の気持ちも変わります。
私自身も、花材選びに迷ったとき「今日は赤でまとめてみようかな」「紫で少し落ち着いた雰囲気にしよう」と、“色”を出発点に作品を考えることがあります。色を意識することで、テーマが明確になり、活ける楽しさもぐっと広がります。
この記事では、いけばなでよく使われる色別におすすめの植物や活け方のヒントをご紹介します。
日々のいけばなに、「色で選ぶ」視点を取り入れてみませんか?
色をテーマにするメリットとは?
いけばなを色で構成することで、次のようなメリットがあります。
-
作品のテーマが明確になる
→「春の赤」「秋の黄」など、ストーリー性が出る -
視覚的なまとまりが生まれる
→同系色で統一することで、作品全体が美しく調和する -
季節感や感情を表現しやすい
→色が持つイメージ(赤=情熱、紫=静けさなど)を活用できる
とくに初心者の方には、「構成をどうするか悩むときに色を決める」方法が取り組みやすくおすすめです。
赤|情熱・生命力・アクセントに
赤の植物の魅力
赤は力強さや情熱、生命の輝きを象徴する色。空間に強いアクセントを与えたいとき、季節感を出したいときにぴったりです。
赤を持つおすすめ植物
| 植物名 | 特徴・使いどころ |
|---|---|
| ナンテン(実) | 秋冬の赤い実が印象的。控えめな葉と好バランス。 |
| ヒペリカム | 赤〜濃ピンクの実が可愛く、作品に動きを加える |
| ベニバナ | 夏に活躍。和の雰囲気と鮮やかさを両立 |
| アカメガシワ | 新芽の赤が美しく、葉ものとしても使用可能 |
活け方のコツ
-
主張が強いため、1〜2点使いが効果的
-
緑や白とのコントラストで際立たせる
-
枝・実タイプはシンプルな構成にも映える
黄|光・明るさ・季節感の演出に
黄色の植物の魅力
黄色は、明るく元気な印象を与える色。春〜初夏に多く、季節の始まりや希望を表現するのにぴったりです。
黄を持つおすすめ植物
| 植物名 | 特徴・使いどころ |
|---|---|
| レンギョウ | 早春の代表花。枝ものとしても華やか |
| ミモザ(アカシア) | ふわふわした花が柔らかい印象に |
| ヤマブキ | 和の花として人気。品のある黄色が魅力 |
| ランタナ | 小さな花が密集し、明るい彩りに |
活け方のコツ
-
青や紫と合わせると“補色の対比”で映える
-
鉢植えで育てやすい種類も多く、日常的に楽しめる
紫|静けさ・品格・余韻を出す色
紫の植物の魅力
紫は静寂・品位・精神性を感じさせる色。和の空間や落ち着いたテーマのいけばなに最適です。
紫を持つおすすめ植物
| 植物名 | 特徴・使いどころ |
|---|---|
| シュウメイギク | 秋の代表花。控えめな紫が上品 |
| フジバカマ | 花も香りも優しく、秋によく合う |
| ムラサキシキブ | 紫の小さな実が美しい。晩秋におすすめ |
| ラベンダー | 香りと色を同時に楽しめるハーブ系植物 |
活け方のコツ
-
白や薄緑と合わせて清楚にまとめる
-
低彩度の色と組み合わせて“静けさ”を演出
白|清らかさ・余白・引き立て役に
白の植物の魅力
白は「無垢・清楚・余白」を象徴します。主役にも引き立て役にもなれる万能な色です。
白を持つおすすめ植物
| 植物名 | 特徴・使いどころ |
|---|---|
| ユキヤナギ | 春の枝ものとして人気。動きのある線が美しい |
| スイセン | 冬〜早春に。黄色との組み合わせも◎ |
| ギボウシ | 白斑入りの葉が涼しげな印象に |
| ハクモクレン | ダイナミックに構成したいときに |
活け方のコツ
-
強い色の花材の“間”に使うと、全体が整う
-
光や陰影を活かした配置にすると印象的
緑|癒し・中間色・構成の支えに
緑の植物の魅力
緑は葉ものを中心としたいけばなの基礎色。他の色を引き立てつつ、構成の骨格にもなります。
緑のおすすめ植物
| 植物名 | 特徴・使いどころ |
|---|---|
| ドウダンツツジ | 線の動きが美しく、夏〜秋に活躍 |
| アイビー | 自由な動きが出せるつる性葉もの |
| ギボウシ | 茂りすぎず、まとまりやすい |
| アジアンタム | 繊細な葉がやわらかい雰囲気を生む |
組み合わせて広がる「色いけばな」の世界
色は単独でも美しいですが、複数の色をどう組み合わせるかによって、いけばなの奥行きや広がりがぐっと深まります。
おすすめ配色例
| テーマ | 組み合わせ例 | 印象 |
|---|---|---|
| 春の彩り | ピンク+黄+白 | 明るく優しい |
| 夏の涼感 | 白+緑+青紫 | さわやか・静けさ |
| 秋の深み | 赤+紫+茶系 | 落ち着き・和風 |
| 冬の静寂 | 白+銀葉+黒枝 | 透明感・余韻 |
色を育てる楽しみ|庭づくり・鉢植えのヒント
いけばなに使う植物を「育てる」ことは、ただ花材を確保する手段ではなく、色そのものを育てるという楽しみにもつながります。
庭や鉢で季節ごとの色彩を育て、時間をかけてじっくりと花材として迎え入れる――それは、いけばなのプロセスにもうひとつの深みを与えてくれます。
色の発色は「育て方」で変わる
植物が本来持つ色は、日照・水分・土壌によって変化します。たとえば、紫系の花(アジサイ、フジバカマ、ラベンダーなど)は、酸性・アルカリ性によって発色が微妙に異なりますし、日照不足だと色が薄くなることもあります。
私の庭では、以前ラベンダーを半日陰で育てていたのですが、なかなか濃い紫にならず、日当たりの良い場所に移したところ、ぐっと色が引き締まりました。
色別・育てると楽しい植物の一例
| 色 | 植物例 | 育てるポイント |
|---|---|---|
| 赤 | ベニバナ、ナンテン、ヒペリカム | 日当たり重視/土壌は排水よく |
| 黄 | ミモザ、ヤマブキ、レンギョウ | 日照が大切/やや乾燥ぎみに管理 |
| 紫 | ラベンダー、フジバカマ、ムラサキシキブ | 日向で育てつつ、水切れに注意 |
| 白 | スイセン、ユキヤナギ、シロタエギク | 半日陰でも育つ/風通しを意識 |
| 緑 | ギボウシ、ドウダンツツジ、アイビー | 暑さ・寒さに合わせて場所を調整 |
庭や鉢で「色ゾーン」をつくる
庭づくりをしていると、つい種類ごとに植えたくなりますが、“色ゾーン”をつくるのも面白い方法です。
たとえば、南側には赤〜橙系の植物、北側には白や緑を中心に植えて、いけばなのテーマごとに花材を集めやすくすると、活ける際の選択肢がぐっと広がります。
ベランダ栽培でも、鉢の色テーマを決めて組み合わせていくと、季節の表情が生まれ、育てる時間にも彩りが加わります。
色テーマ別・いけばな作品づくりのヒント
「色」をテーマにいけばなを考えると、作品にストーリーが生まれます。
ここでは、私自身が実際に活けてきた色テーマ別の作品例をいくつかご紹介します。
1. 赤×白×緑|お正月やお祝いの花
使用花材:ナンテン(赤い実)、ユキヤナギ(白)、アオキ(斑入り葉)
お正月やお祝いの場にぴったりな構成です。赤と白は対照的ながら調和し、緑が全体をつなぎます。
花器は黒や朱塗りのものを使うと、より引き締まった印象に。
2. 紫×白|和室に合う静かな作品
使用花材:シュウメイギク(紫)、スイセン(白)、シラカシ(葉もの)
茶席や和室の床の間に合う構成。紫の花は控えめながら存在感があり、白がその静けさを際立たせます。
枝ぶりで動きを出すよりも、高さの差と空間の余白を意識するとバランスが整います。
3. 黄×緑×白|春の始まりを告げる組み合わせ
使用花材:レンギョウ(黄)、ギボウシ(葉)、ユキヤナギ(白)
春先におすすめの明るい作品。黄色の花は上部、緑の葉を中段、白い小花を足元に散らすように配置することで、立体感のある構成になります。
鉢植えで育てたものをそのまま剪定して使える花材が多く、「育てる+活ける」のサイクルが自然に実践できます。
4. 青紫×シルバーリーフ|夏の涼感いけばな
使用花材:ラベンダー(青紫)、シロタエギク(白銀葉)、アジアンタム(緑)
暑い季節にぴったりの“見た目の涼しさ”を重視した構成です。
光沢感のある葉や淡い色彩を取り入れることで、視覚的な清涼感が生まれます。
ガラスの花器や、涼やかな音を感じさせる空間に合わせると、より涼感を引き立ててくれます。
このように、色を軸にしていけばなの構成を考えることで、植物選びが明確になり、育てる楽しさと活ける楽しさがつながるのが魅力です。
次の作品では、ぜひ色をテーマにした構成に挑戦してみてください。
日本文化に息づく「色」と植物の関係
いけばなを学んでいると、ただ「美しさ」を追求するだけでなく、色や植物に込められた意味や文化的背景に触れる場面が多くあります。
日本では古くから、色には特別な象徴性があり、花や植物と深く結びついて使われてきました。
このセクションでは、いけばなと日本文化をつなぐ「色の意味」に注目し、花材選びに活かせるヒントをご紹介します。
和の色に込められた意味とは?
日本には「伝統色」と呼ばれる豊かな色の世界があります。それぞれの色には長い歴史や精神性があり、儀礼・行事・季節感とも結びついています。
| 色 | 意味・象徴 | 使われる場面 |
|---|---|---|
| 赤 | 魔除け・祝福・生命力 | お祝い・初詣・祭事など |
| 白 | 清らかさ・始まり・喪 | 仏事、正月、結婚式など |
| 紫 | 高貴・知性・敬意 | 茶席、寺院、格式ある場面 |
| 黄 | 豊穣・繁栄・希望 | 春祭り、端午の節句など |
| 緑 | 平穏・再生・自然との調和 | 日常・季節の中の安らぎ |
たとえば、「赤」は祝いごとに欠かせない色ですが、古来は魔除けの色とされ、子どもの産着や正月飾りにも多く使われてきました。
行事や風習に見る「色と花材」
いけばなでも、色と季節行事の関係を意識することで、作品に深みが加わります。
● 正月|紅白で祝いの気持ちを
松・ナンテン・ユキヤナギなど、赤・白・緑を組み合わせた正月飾りは、無病息災や家内安全を願う気持ちを表現しています。
紅白の構成は、明快でわかりやすく、日本人にとってとてもなじみ深い配色です。
● お盆や仏事|白で静けさを演出
スイセンやユリ、キキョウなどの白い花は、清らかさや鎮魂の象徴とされ、仏花としてもよく使われます。
いけばなでも、白花を主とした静謐な構成にすることで、静けさや祈りの空気を作品に込めることができます。
● 秋の重陽|紫で長寿と品格を
9月9日の「重陽の節句」は、菊を活ける行事として知られます。とくに紫の菊は、高貴さと長寿の願いを込めた花材として重宝され、茶道でも尊ばれています。
色の「重なり」による物語性
いけばなでは、単色ではなく色の重なり・調和によって、作品の奥行きや意味が深まります。
たとえば、赤と緑は対比的な色ですが、正月飾りに使うと「祝いと自然の調和」を表現できます。
また、白い花に紫の葉を添えると、「静けさの中に気品がある」といった繊細な物語が生まれます。
このような文化的な色の使い方を知っておくと、作品を活けるときに、より豊かな表現ができるようになります。
私の体験より|「色の意味」で伝わる気持ち
ある冬の日、白いスイセンとアオキの緑、そしてほんの少しの赤実(ナンテン)を使って作品を活けたことがあります。
当時、友人を励ましたいという気持ちがあり、「清らかな気持ち(白)」「生命のエネルギー(赤)」「安定(緑)」を込めた構成にしました。
後日、その友人から「見るとほっとする」「元気が出る」と言ってもらい、色を通じて気持ちが伝わったように感じたのです。
いけばなにおいて、色は単なる装飾ではなく、感情や願いを形にする手段にもなり得ると感じた出来事でした。
文化の視点で広がる“色いけばな”
いけばなに使う色や植物は、ただ目に美しいだけでなく、文化や想いを映す鏡でもあります。
赤には祝いの気持ちを、白には祈りを、紫には敬意を――そんなふうに色の意味を意識して植物を選ぶことで、作品がより豊かに、深く心に響くものになります。
色を育て、色で活け、色で伝える――。
あなたのいけばなにも、ぜひ「色に込めた物語」を重ねてみてください。
よくある質問Q&A|色の選び方に迷ったら?
Q. 色をそろえるのと、複数色を使うのと、どちらがよいですか?
A. どちらも良さがあります。初心者には「同系色でまとめる」のが簡単で、慣れてきたら補色や差し色を取り入れてみるのもおすすめです。
Q. 家で育てた植物を色ごとに分類するコツは?
A. 「花の色」だけでなく、「実や新芽の色」もヒントになります。時期によって色が変化する植物もあるので、育成中に写真を残すのも◎。
Q. 色がかぶらないようにしたいときは?
A. グリーンや白で“抜け”をつくることで、強い色同士のバランスをとることができます。
まとめ|「色」で選ぶと、いけばながもっと楽しくなる
いけばなは「構成」や「花器」だけでなく、色という視点からも自由に楽しめる芸術です。
色を意識することで、作品にテーマが生まれ、感情や季節感もより豊かに表現できるようになります。
まずは、自分が「いいな」と感じる色から始めてみてください。きっと、いけばなの楽しみ方がもう一段広がるはずです。