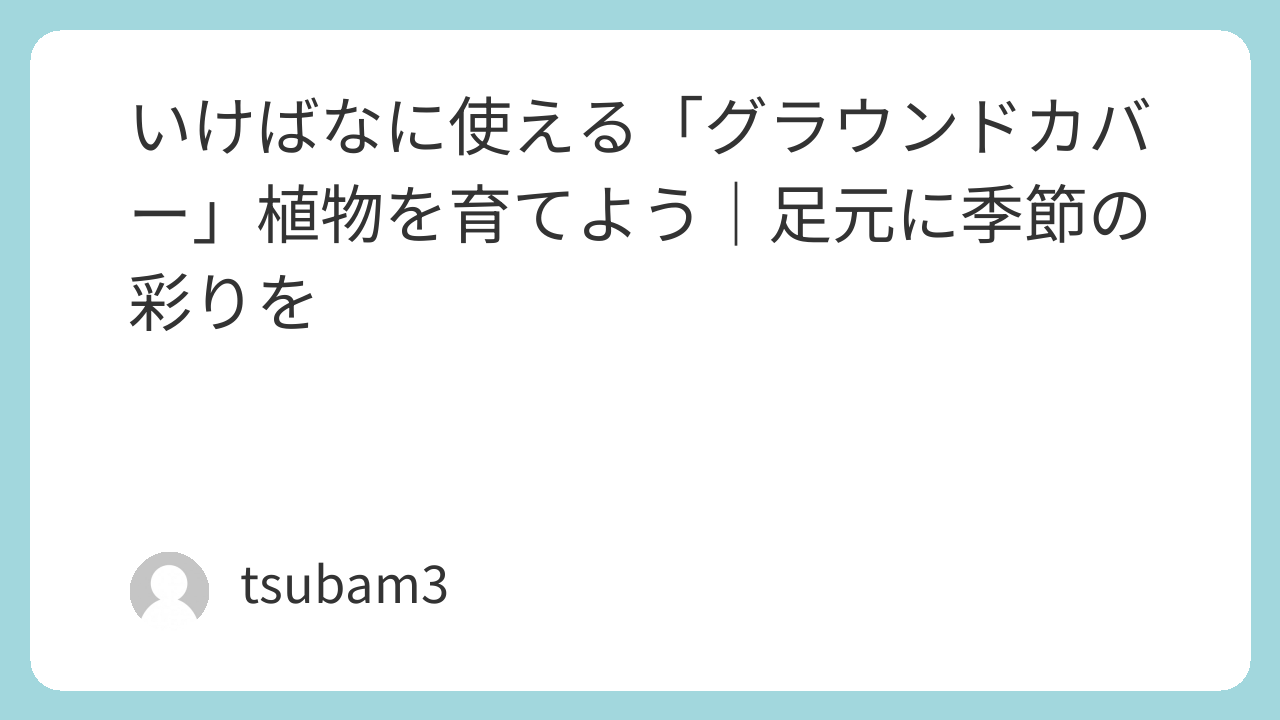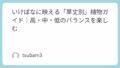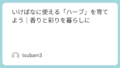はじめに|いけばなにおける「足元」の演出
いけばなを習いはじめてしばらく経ったころ、「作品の足元」にもう少し自然な広がりがほしい……と感じるようになりました。
そのとき出会ったのが、グラウンドカバー植物です。
本来は庭の土を覆うための植物ですが、低く這うような葉姿や繊細な花が、作品に柔らかなリズムや広がりを与えてくれます。
この記事では、いけばなに活用できるグラウンドカバー植物の育て方・使い方・おすすめ品種を、初心者にもわかりやすく紹介します。
- グラウンドカバー植物とは?
- 育てやすくて使いやすい!おすすめグラウンドカバー植物7選
- 育て方の基本|庭でも鉢でも楽しめる!
- グラウンドカバー植物の活け方|草丈とのバランスを取るヒント
- 季節別に楽しむいけばな向けグラウンドカバー植物
- グラウンドカバー植物を使ったいけばな作品実例
- グラウンドカバー植物の育て方と暮らしでのいけばな活用
- 日本庭園の下草文化といけばなにおけるグラウンドカバーの役割
- グラウンドカバー植物で楽しむ「育てて活ける」いけばなの循環
- 体験談|自宅で育てたグラウンドカバー植物をいけばなに活用
- よくある質問Q&A|いけばな初心者にも安心!
- まとめ|いけばなに「足元の彩り」を
- エッセイ風あとがき|足元に目を向けると、見えてくるもの
グラウンドカバー植物とは?
地面を覆い、景観と環境を整える植物
「グラウンドカバー」とは、地表を覆うように広がる性質を持つ草花のこと。
もともとは雑草防止や土壌保護、景観の補強などに用いられますが、そのコンパクトさ・広がり方・花や葉の個性から、いけばなにおいても非常に魅力的な存在になります。
いけばなとの相性
-
低い位置で彩りを添える
-
枝ものや主花の「足元」を自然に演出
-
花器の縁や水際にそっと添えることで「野の風景」感を表現
育てやすくて使いやすい!おすすめグラウンドカバー植物7選
以下に、いけばなに活かしやすく、家庭で育てやすいグラウンドカバー植物を表で紹介します。
おすすめ品種一覧表
▼ 以下の表で、育てやすさや活け方のポイントをチェック!
| 植物名 | 特徴 | 開花期 | 活け方のポイント | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤープランツ | 丸い葉が可愛く、這うように伸びる | ―(花は目立たない) | 枝物の足元にふわっと広げて | ◎初心者向け |
| タイム(クリーピング系) | 香り良く、初夏に花も咲く | 5〜6月 | ナチュラルな草ものと相性良し | ○ |
| リシマキア・ヌンムラリア | 黄緑の葉が明るくアクセントに | 5〜7月 | 作品の明度調整に便利 | ◎ |
| セダム(万年草系) | 多肉質で乾燥に強い | 種類により通年 | 水際にも強く、短期活けに向く | ◎ |
| ベロニカ・オックスフォードブルー | 青花とつややかな葉が魅力 | 4〜5月 | 春の作品に彩りを添える | ○ |
| アジュガ | 濃い葉色と初夏の花穂が特徴 | 4〜6月 | 落ち着いた雰囲気に合う | ○ |
| ヒメツルソバ | 丸いピンクの花がユニーク | 春〜秋 | 作品に遊び心を加えたいときに | △繁殖力注意 |
育て方の基本|庭でも鉢でも楽しめる!
1. 用土と鉢選び
-
水はけの良い土を選ぶ(市販の草花用培養土でOK)
-
地植えの場合、直射日光〜半日陰の場所を選ぶ
-
鉢植えでは広がりを意識して浅鉢や横長プランターもおすすめ
2. 水やりと管理
-
基本は乾いたらたっぷり
-
蒸れやすい夏は風通しに注意
-
多肉系(セダムなど)は乾燥気味でもOK
3. 剪定と株分け
-
伸びすぎたらカットして形を整える
-
春・秋に株分けすればどんどん増える
-
剪定した枝はそのままいけばなに活用できるのが魅力!
グラウンドカバー植物の活け方|草丈とのバランスを取るヒント
基本は「主花材の足元」に自然に添える
-
枝ものや大きめの花材と組み合わせて、草丈差による立体感を演出
-
花器の縁や、正面から見て視線の抜ける位置に配置すると自然
こんな使い方もおすすめ
-
【小品花】の足元にあしらって「野辺の一輪風」に
-
水盤の縁から垂れさせて「野趣」を表現
-
花材が少ないときの空間補填や質感の足し算にも便利
季節別に楽しむいけばな向けグラウンドカバー植物
いけばなは、季節を表現する芸術。
グラウンドカバー植物を取り入れることで、「足元から季節感を演出する」ことができます。ここでは、春夏秋冬それぞれにおすすめの植物を、開花や葉色の変化とともにご紹介します。
🌸 春|やわらかな芽吹きと可憐な花を
| 植物名 | 特徴 | 活け方のヒント |
|---|---|---|
| ベロニカ・オックスフォードブルー | 小さな青花が春風のように揺れる | 主役の花材の足元に、軽やかに添えて |
| ヒメツルソバ | ピンクの小花がぽこぽこと咲く | モダンな器にあしらえばアクセントにも |
☀ 夏|緑の広がりと爽やかさ
| 植物名 | 特徴 | 活け方のヒント |
|---|---|---|
| タイム(クリーピング) | 香り高く、茎が自然に垂れる | ハーブとして香りも楽しめる作品に |
| リシマキア・ヌンムラリア | 明るい黄緑が涼しげ | 黒系の器と合わせて夏らしく演出 |
🍁 秋|深みのある色と落ち着き
| 植物名 | 特徴 | 活け方のヒント |
|---|---|---|
| アジュガ | ブロンズ系の葉が秋に映える | 枝ものと合わせて、地面の色を意識した演出に |
| セダム(紅葉するタイプ) | 赤やオレンジに色づく | 短く切って、小品作品に添えると効果的 |
❄ 冬 |常緑の存在感と静けさ
| 植物名 | 特徴 | 活け方のヒント |
|---|---|---|
| ワイヤープランツ | 冬も葉を落とさず青々としている | 葉の丸みで、冷たさの中にやさしさを演出 |
| ヘデラ(アイビー) | つる性で動きが出しやすい | 器の縁に垂らすことで空間に広がりが出る |
グラウンドカバー植物を使ったいけばな作品実例
ここでは、実際にグラウンドカバー植物を使って活けた私の作品やアイデアをご紹介します。足元に少しの緑を加えるだけで、作品全体の印象がガラリと変わるのを体感できました。
実例①:山路の風景を表現した「枝もの+ワイヤープランツ」
花材:コデマリの枝、ワイヤープランツ、ヒペリカム
花器:黒の楕円形水盤
ワイヤープランツを水盤の縁から少し垂らし、「山道に沿って伸びる草」のイメージで活けました。枝の野性味と丸い葉の柔らかさが絶妙にマッチし、鑑賞者からも好評だった一作です。
実例②:ハーブと野の花のさりげない共演
花材:ナツハゼ、タイム、ヤマアジサイ
花器:白い陶器の筒型
タイムの香りがふわっと漂い、目に見えない“香りの演出”まで叶いました。小さな作品ながらも、足元のハーブがナチュラルな余白を生み、作品に奥行きを与えてくれました。
実例③:秋の静けさを感じるセダム使い
花材:ツルウメモドキ、セダム(オータムジョイ)
花器:ガラス製の平皿
紅葉したセダムを切り花のように短く切って配置したことで、まるで落ち葉が舞い降りたような情景に。秋らしい余韻を漂わせる演出ができました。
グラウンドカバー植物の育て方と暮らしでのいけばな活用
いけばなに使えるグラウンドカバー植物は、庭や鉢植えでも楽しめる万能選手です。育てて、眺めて、活けて――暮らしの中で何度も登場してくれる存在になります。
植物のある日常で、こんな楽しみ方も
-
鉢の中で自然風の寄せ植えに
→ 背の高い植物の根元にタイムやリシマキアを添えると、見た目にも美しく、水はけも保てます。 -
花が終わったあとも残る葉の美しさ
→ 春の花が終わったあとのベロニカやアジュガの葉が、長く緑を保ち、作品の背景づくりにも活躍。 -
グリーンの“切り戻し”がそのまま作品に
→ 伸びすぎたら切る→いけばなに使う→また伸びる…という循環型の楽しみが生まれます。
シェアできる喜びも
-
剪定した枝を小鉢に挿して「おすそ分け」
-
同じ教室の方と交換して「育ててから活ける」を共有
-
子どもや家族と一緒に植えて育てる楽しみを分かち合う
植物を通じたつながりが広がるのも、グラウンドカバーならではの魅力です。
日本庭園の下草文化といけばなにおけるグラウンドカバーの役割
グラウンドカバー植物をいけばなに取り入れていると、ふと日本庭園の「下草(したぐさ)」を思い出すことがあります。
庭における下草は、主木や石組みを引き立てながらも、風景の自然さや季節感を支える“背景の名脇役”です。
和の庭園に見る下草の役割
-
主木の足元にスギゴケを敷くことで落ち着きと静けさを演出
-
ヤブコウジやヒメツルソバが庭の陰影や移ろいを感じさせる
-
下草があることで、庭全体が平面的でなく、立体的な風景となる
この考え方は、いけばなにも通じます。
枝ものや花材を際立たせるために、足元に添えるグリーンがあると、作品がぐっと引き締まるのです。
いけばなに応用するメリット
-
花材の「根元」を隠すことで作品が自然に見える
-
下草があることで「時間の流れ」や「場の空気感」を表現できる
-
草ものだけで構成した“現代的な野花のいけばな”にも応用可能
とくに「草丈の低い植物」=グラウンドカバー植物は、日本庭園の下草的役割をいけばなの中で担うことができます。
単なる“飾り”ではなく、「空間をつくる」素材として意識してみてください。
グラウンドカバー植物で楽しむ「育てて活ける」いけばなの循環
グラウンドカバー植物の多くは、丈夫で増えやすいのが魅力です。
しかも、切った枝をそのまま活けられるという性質上、いけばなをしている人にとっては**“素材の循環”ができる植物**でもあります。
育てて、活けて、増やして、また使う
-
タイムやリシマキアは切り戻しで新芽が増える
-
セダムやヒメツルソバは挿し芽で簡単に根づく
-
ワイヤープランツも水差しで根が出る→再利用可能
「いけばなで使ったあとの枝を、もう一度土に戻す」
そんな自然なサイクルが、自宅の小さな鉢の中でも楽しめます。
育てた植物を“おすそわけ”してみよう
-
増えた枝を小鉢に挿してプレゼント
-
教室の仲間と「この植物、活けやすいよ」と情報交換
-
いけばな展で「自分で育てた植物です」と伝えると話題にも!
私自身、剪定したワイヤープランツを小瓶に挿して教室に持って行ったところ、「これ、かわいいね」「欲しい!」と反響があり、そこから植物の話が広がったことが何度もあります。
小さな循環が、いけばなをもっと楽しくする
グラウンドカバー植物は、暮らしといけばなをやさしくつなぐ植物。
毎日眺めて育てた植物を、ある日ふと一枝活けてみる。
その一枝が作品を彩り、人との会話を生み、また鉢へと戻っていく――。
そんな“いけばなと共にある植物の循環”は、時間の流れと自然の恵みを感じさせてくれます。
体験談|自宅で育てたグラウンドカバー植物をいけばなに活用
私が最初にいけばなに使ったのは、自宅の鉢から伸びた「ワイヤープランツ」でした。
いつもの枝ものに少し添えてみたところ、それだけで作品に柔らかさと自然味が加わり、とても新鮮に感じたのを覚えています。
以来、鉢で育てる→活ける→また伸びるというサイクルがとても楽しくなり、少しずつ品種も増やしてきました。
いけばなとグリーンのある暮らしの相性は、本当に良いなと実感しています。
よくある質問Q&A|いけばな初心者にも安心!
Q. グラウンドカバーって、どれも横に広がりすぎませんか?
A.育てる環境によって調整可能です。鉢植えで制限すればOK。剪定で小さく保てます。
Q. 土がついていて扱いにくくない?
A.活ける前に洗って水切りすれば、清潔に使えます。根を落とせば「一枝」として使えます。
Q. 冬はどうなりますか?
A.多年草が多いですが、地上部が枯れても春に芽吹くものが多く、季節の変化を楽しめます。
Q. 他の花材と合わせると、グラウンドカバーが浮いて見えませんか?
A. 葉の色味や器の選び方で自然になじみます。
主花材に近いトーンでまとめたり、間に葉ものを挟むと全体の調和がとれます。
まとめ|いけばなに「足元の彩り」を
グラウンドカバー植物は、いけばなにおいて作品の足元を整え、自然な広がりや季節感を加える頼もしい存在です。
しかも、自宅で育てて繰り返し使えるという点で、日々のいけばなをより身近に、豊かにしてくれます。
エッセイ風あとがき|足元に目を向けると、見えてくるもの
いけばなを学びはじめたころ、どうしても「主役の花」ばかりに目がいっていました。枝の形、花の色、器とのバランス……。
けれどある日、先生がそっと添えた一枝の草に、作品全体がふわりと和らいだのを見て、ハッとしました。
そのとき使われていたのが、グラウンドカバーにもなる「アジュガ」でした。
地面を這うような濃い葉が、枝の勢いを受け止め、作品に重心と季節感を与えていたのです。
それ以来、私は草花の「足元」にも心を配るようになりました。
足元に咲くもの、這うもの、広がるもの。
それらは、私たちの暮らしや心のあり方とも、どこか重なっているように思えるのです。
いけばなの足元は、自分自身の足元。
グラウンドカバー植物を育て、活けながら、そんなことを少しずつ感じるようになりました。