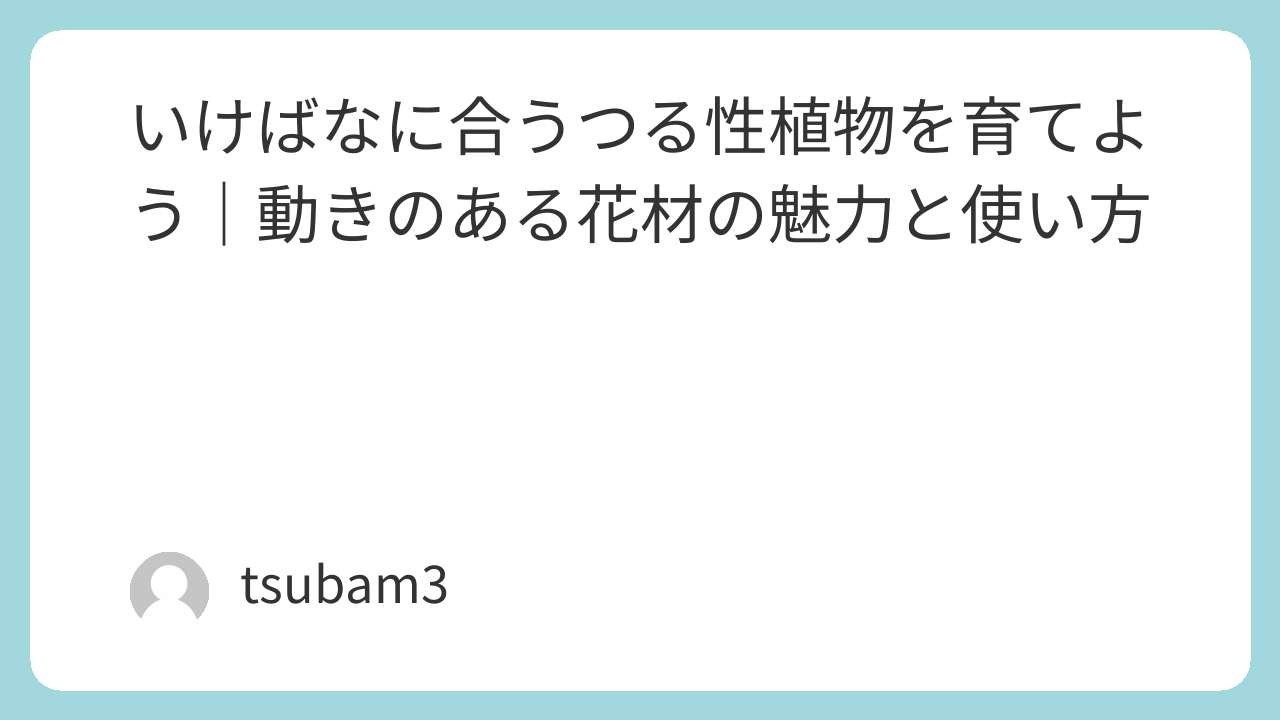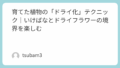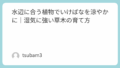はじめに|「つる」は線の美しさを見せてくれる
いけばなを続けていると、「もう少し線の動きが欲しいな」と感じることがあります。そんなとき、自然な曲線や空間の流れを生み出してくれるのが、つる性植物です。
私自身、庭で伸びていくアサガオのつるを見て、「この伸びやかさ、活けてみたいな」と思ったのがきっかけで、つる性植物をいけばなに取り入れるようになりました。
この記事では、いけばなに向いたつる性植物を育てる方法や、作品での活かし方について、私の体験もまじえてご紹介します。
- つる性植物の魅力とは?
- 育てやすいつる性植物植物7選(いけばな向け)
- つる性植物の育て方のコツ
- 作品への取り入れ方|つるで空間をデザインする
- つる性植物で作品を構成するには?|実例で学ぶデザインパターン
- 季節ごとのおすすめつる性植物と植物と活け方アイデア
- 私のつる性植物いけばな体験記|“線”を育てるということ
- つるをドライにして楽しむ|活け終わった後も使える植物たち
- つる性植物を育てるときの注意点と管理のコツ
- つる性植物×他の花材|おすすめの組み合わせ例
- 家庭で楽しむ!つる性植物いけばな活用アイデア
- よくある質問Q&A|つる性植物をいけばなに使うには?
- 自然と向き合う、いけばなの時間|つるを育てるという、ささやかな喜び
- まとめ|線の動きを、育てるところから楽しもう
つる性植物の魅力とは?
自由な動きと“抜け感”を生む
つる性植物の最大の魅力は、そのしなやかな動きです。枝のような直線的な素材とは違い、自然に曲がったり絡まったりする姿が、作品にリズムや柔らかさを与えてくれます。
高さや広がりを補える
棚やフェンスに沿って上に伸ばす、または垂れ下がるように下げるなど、空間の演出にも幅広く活躍します。主役にも、添えとしても使える便利な存在です。
育てやすいつる性植物植物7選(いけばな向け)
| 植物名 | 特徴 | 開花期 | メモ |
|---|---|---|---|
| アサガオ | 朝に花が咲き、つるの動きが軽やか | 夏 | 夏の風情と線の美しさを表現 |
| フウセンカズラ | 実ものも楽しめる軽やかなつる | 夏〜秋 | 緑の実もアクセントになる |
| スイートピー | 春らしい香りと柔らかな花弁 | 春 | つると花を同時に活けられる |
| クレマチス | 花も葉も美しく装飾性が高い | 初夏〜秋 | 和洋両方の作品に使いやすい |
| ヤマノイモ(自然薯) | 茎の曲がりが独特で風情あり | 夏〜秋 | 根茎も生かせば作品に深みが出る |
| ノブドウ | 秋に実をつけ、つるも自在に使える | 秋 | 実もの+線の構成に活躍 |
| カロライナジャスミン | 花付きのよいつるで初心者向け | 春 | 黄色の花が作品に明るさを添える |
つる性植物の育て方のコツ
支柱やネットで「絡ませる」環境づくりを
このタイプの植物は、からむ対象があると自然に伸びていきます。支柱・フェンス・麻ひもなどを使い、絡ませながら育てましょう。
剪定と収穫は「柔らかいつる」を狙って
つる性植物は、成長にともなって茎やつるの一部が木質化(もくしつか)してくることがあります。いけばなに使う場合は、この木質化が進む前の柔らかくしなやかなつるを選びましょう。
曲げやすく、傷みにくいため、空間構成もしやすくなります。
鉢植えでも地植えでも育てられる種類が多い
アサガオやフウセンカズラなどは、プランター栽培にも適応でき、伸びる植物の中でも初心者におすすめです。
作品への取り入れ方|つるで空間をデザインする
垂れ下がるラインを活かす
細口の花器や吊るし型の器を使い、つるが自然に垂れ下がる様子を活けると、軽やかな印象に仕上がります。
絡みや交差で“動き”を加える
あえて交差するように組むと、動きのある立体構成になります。硬い枝ものと組み合わせると、動と静のコントラストが生まれます。
花と実を活かすダブル使い
ノブドウやスイートピーのように、**つる+花(または実)**の要素がある植物は、1本で表情が豊かになりやすく重宝します。
つる性植物で作品を構成するには?|実例で学ぶデザインパターン
いけばなにおいて、つる性植物は“添えるだけ”の存在に思われがちですが、実は主役としても構造的な支えとしても使える万能な花材です。ここでは、私が実際に試してみた構成例を3つご紹介します。
パターン1:つるを“主枝”に見立てる構成
-
使用例:クレマチスの長いつる × アジサイの花
-
構成:クレマチスのつるを大きく弧を描くように配置し、その線に寄り添うようにアジサイを配置。
-
ポイント:花器は低め・口広のものを選び、つるの動きが映えるように空間をたっぷり取ると効果的です。
パターン2:主枝に“絡める”構成
-
使用例:ドウダンツツジの枝 × ノブドウのつる
-
構成:枝を主軸に立て、ノブドウのつるを自然に絡ませる。
-
ポイント:つるの柔らかさを活かして「一部だけ巻きつける」ようにすると、強弱のある線が生まれます。
パターン3:添え草的に“足元に広げる”構成
-
使用例:スイートピーのつる × アリウム(直立の花)
-
構成:直線的な花の足元に、ふんわりとつるを絡めて視線の流れを下へつなぐ
-
ポイント:足元に動きを加えると、作品全体が**“土に根ざした自然”のような印象**になります。
季節ごとのおすすめつる性植物と植物と活け方アイデア
季節で表情が変わるつる性植物は、四季折々で育てられる種類が変わり、活け方の表情も違ってきます。以下のように、季節ごとの「おすすめ植物」と「活け方のヒント」をまとめてみました。
| 季節 | 植物名 | 特徴・使い方のヒント |
|---|---|---|
| 🌸春 | スイートピー カロライナジャスミン |
やわらかなつると香りを活かして 透明感のある器に垂らすように活ける |
| ☀夏 | アサガオ フウセンカズラ |
線の動きが活きる時期。 あえて水に浮かべる演出も◎ |
| 🍁秋 | ノブドウ ヤマノイモ |
実ものと色合いで深みのある構成に。 絡ませ系の器で空間に“物語”を加える |
| ❄冬 | ツルウメモドキ(剪定枝) オキナワスズメウリ(乾燥向き) |
実の鮮やかさや乾いた質感を強調。 ドライ風に仕上げても風情あり |
私のつる性植物いけばな体験記|“線”を育てるということ
私が伸びゆく植物に惹かれるようになったのは、ある夏の日のことでした。
庭のフェンスに絡んだアサガオが、朝の光に照らされて、するすると空へ向かって伸びていたのです。その姿は、まるで目に見えない音楽に合わせて踊っているようで、見とれてしまいました。
「この動きを、作品に取り込めないだろうか?」
そう思い、咲き終わった後の柔らかいつるを一枝、そっと切ってみました。花器に活けると、それまで使っていた枝や花にはない“しなやかさ”が加わり、空間がふわっと軽くなるような、不思議な感覚がありました。
それからというもの、フウセンカズラやノブドウ、ジャスミンなどを少しずつ育てては、つるの流れを意識して活ける練習を重ねています。
曲げようとしても言うことを聞かないこともあるし、予想と違う曲がり方になることもある。でも、それもまた植物の自然な“線”であり、自分がそれをどう活かせるかが、いけばなの面白さだと感じるようになりました。
いけばなは「切った植物を活ける」だけでなく、「線を育てる」ところから始まっているのかもしれません。
つるをドライにして楽しむ|活け終わった後も使える植物たち
一部のつる植物の中には、活け終わったあとに乾燥させてドライ化しやすいものもあります。再利用してリースやアレンジ作品に活かすのも、いけばなを長く楽しむ工夫の一つです。
ドライ向きのつる性植物例
-
ノブドウ:実の色は乾燥でやや褪せますが、つるの形状は維持しやすい。
-
ヤマノイモ(自然薯):乾いてもしなやかさが残り、構成しやすい。
-
スズメウリ(オキナワスズメウリ):小さな実が可愛らしく、リースにも◎。
ドライ化のポイント
自然な形のまま、乾かすには?
– 風通しのよい日陰に吊るす(直射日光は退色しやすい)
– 絡まる前に、形を整えてから乾燥すると、構成に使いやすい
– 完全に乾いたら、埃を払い、スプレーニスで保護するのもおすすめ
自然に枯れていく姿も、またいけばなの一部。活け終わった植物にも“第二の舞台”を用意してあげるような感覚で、ドライ化に挑戦してみてください。
つる性植物を育てるときの注意点と管理のコツ
このタイプの植物は比較的育てやすいものが多いですが、いけばなに使うことを前提とした場合、「伸ばしすぎない」「美しい状態を保つ」ためのちょっとしたコツがあります。
1. 伸ばしすぎないことが大切
つるは自由に伸びますが、放っておくと絡まりすぎて使いにくくなることも。花材として活けたい場合は、ある程度の長さで剪定して整える習慣をつけると、柔らかく美しいつるを維持できます。
-
目安:50〜70cmほどで一度カットすると、扱いやすく再生もしやすい
-
横に広がる場合は支柱やトレリスに誘引して管理
2. 虫害・病気に注意
葉が茂りやすいつる性植物は、アブラムシやハダニが発生しやすい傾向にあります。無農薬で育てたい場合は、以下の方法で予防しましょう。
-
植物の間を風通しよく保つ
-
牛乳スプレーや木酢液など、天然素材の防虫対策を試す
-
被害が出た葉やつるは早めに剪定して対処
3. 水切れに注意
つる性植物は、根からしっかり水を吸い上げて伸びるため、水切れすると葉がしおれやすくなります。とくに鉢植えの場合は、夏場の朝夕の水やりを忘れずに。
🌱 活ける予定がある日の前日は、たっぷり水を与えておくと、ハリのある美しい状態で収穫できます。
つる性植物×他の花材|おすすめの組み合わせ例
いけばなでつる性植物を活かすには、他の花材との**“相性”**も大切です。ここでは、私が試してきた中で、特に印象的だった組み合わせをいくつかご紹介します。
クレマチス × アジサイ
-
初夏の爽やかな組み合わせ。クレマチスの動きでアジサイの重みを軽やかに補う。
-
白系の花器を使うと、上品な印象に仕上がる。
フウセンカズラ × ミズヒキソウ
-
両方とも繊細な線を持つため、草もの同士の軽やか構成に。
-
ガラスの細口花器で涼しげに活けるのがおすすめ。
ノブドウ × ヒオウギ
-
秋に映える色の対比が美しい。
-
実の紫とヒオウギの朱色が、和の色彩構成を引き立てる。
アサガオ × ギボウシの葉
-
アサガオの花やつると、大きな葉ものを合わせると夏らしい力強さが出る。
-
低めの器でもボリュームが出しやすい。
家庭で楽しむ!つる性植物いけばな活用アイデア
つる性植物をいけばなに使うというと、少し構えてしまう方もいるかもしれません。でも実際には、日常の中で気軽に楽しめる方法もたくさんあります。ここでは、初心者にもおすすめの活用アイデアをいくつかご紹介します。
1. 小さな瓶やグラスに一枝だけ
つるの一枝をガラス瓶に挿すだけで、夏らしい風情のあるミニいけばなが完成します。とくにフウセンカズラやアサガオのつるは、軽やかさと可愛らしさがあるので、小さなスペースにもよく合います。
2. 窓辺や棚の上に「垂らす」演出
棚の端や窓辺に、小さな器を置いて、つるが垂れ下がるように活けると、視線の流れを柔らかく演出できます。スイートピーやクレマチスなどの花付きのものを使うと、香りや彩りも加わります。
3. お子さんと一緒に育てて活けてみる
つる性植物は育ちが早く、変化が目に見えやすいため、観察日記や夏休みの自由研究にもぴったりです。親子で一緒に育てて、収穫して、いけばなとして飾るという流れは、自然とのふれあいの機会にもなります。
このように、つる性植物はいけばなの枠をこえて、暮らしの中で自由に楽しめる存在です。決して大きな花器や本格的な構成がなくても、植物が持つ「線」や「流れ」を日常の中で感じながら、ひと枝活けてみる。そんなシンプルないけばなの楽しみ方も、つる性植物だからこそ味わえる魅力です。
よくある質問Q&A|つる性植物をいけばなに使うには?
Q. つるが折れてしまいやすいのですが…?
A. 収穫時に根本からではなく、節の少し上をハサミで切り、ゆっくりと水揚げしてください。活けるときも無理に折り曲げず、自然な流れを活かしましょう。
Q. つるが暴れて形が整いません。
A. 花留めやワイヤーで軽く位置を補助するのがコツです。すべてを固定せず、少し遊びを残すと自然な動きになります。
Q. 花がすぐしおれる気がします。
A. つる性植物は葉の蒸散が多いため、活ける直前に水につけて水揚げし、涼しい場所に置くと持ちが良くなります。
自然と向き合う、いけばなの時間|つるを育てるという、ささやかな喜び
植物を育てる中で、つる性植物は少し特別な存在です。気がつけばどこかに絡まり、思いもよらない方向に伸びていく。それは、まるで「植物が自分の意思を持っているかのような」自由な動きです。
その動きを活けるということは、自然のままの線を受け入れることでもあります。「もっと曲がってほしい」「ここで止まってほしい」と思っても、思い通りにならない。でも、だからこそ面白い。
いけばなは、思い通りに構成する芸術ではなく、自然と対話しながら“共につくる”表現なのだと、私はつる性植物を活けるたびに感じます。
そんな“線の芸術”を、自分の庭や鉢で育てることから始めてみませんか?
まとめ|線の動きを、育てるところから楽しもう
つる性植物は、いけばなに「線の美しさ」「動き」「空間の流れ」を加えてくれる、まさに“生きたデザイン素材”です。庭や鉢で育てたつるを活けることで、自分の手で作った線を表現する楽しみも広がります。
ふと見上げたフェンスのアサガオ、絡みつくように育つノブドウ――そんな植物たちを、次は一枝、花器に活けてみませんか?