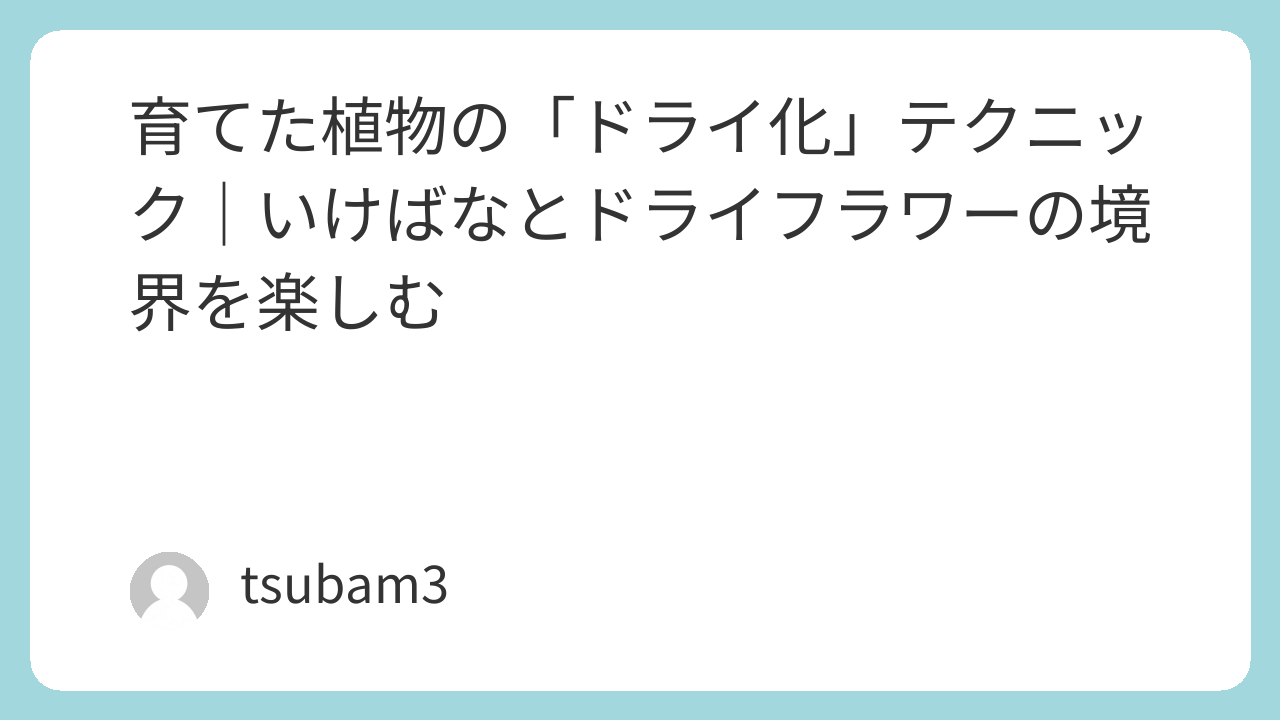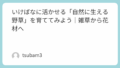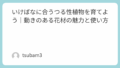はじめに|「枯れていく美しさ」も、いけばなの一部
いけばなを続けていると、季節の移ろいとともに、植物の姿が変わっていくのを自然に受け入れるようになります。咲いた花が終わり、葉が色づき、茎が乾いていく――そんな過程にも、美しさや意味が宿っていると感じるようになるのです。
私自身、庭で育てた植物を活けたあと、「すぐに捨てるのはもったいないな」と思ったことがきっかけで、ドライ化という選択肢に出会いました。乾いていく植物を、もう一度いけばなに取り入れる。そこには、生花とはまた違った面白さと奥深さがあります。
この記事では、育てた植物を乾燥させて再活用するテクニックと、その魅力的な活かし方について、私の経験も交えながらご紹介します。
- ドライ化ってなに?|自然乾燥で楽しむ植物の“第二の命”
- 育てた植物を乾かして活かすメリット
- よく使う植物乾燥のテクニック3選
- ドライ化した植物の活かし方|いけばな×ドライの新しい提案
- 私の体験談|「枯れる」という美しさを受け入れる
- ドライ化しやすい植物10選|いけばなにも使える素材たち
- ドライ化の失敗談と対策|“枯らす”を“活かす”に変えるヒント
- 失敗から生まれる、“あなたらしい乾いた美”のかたち
- 四季を彩るドライ素材のいけばな活用法|四季の“余韻”を飾る楽しみ
- 季節を「乾かして残す」という発想
- よくある質問Q&A|初心者でもできる?
- コラム|私のドライ化実験記|フジバカマと秋の午後
- まとめ|いけばなと“乾いた花材”、そのあわいを楽しもう
ドライ化ってなに?|自然乾燥で楽しむ植物の“第二の命”
ドライ化とは、植物を乾燥させて、長く楽しめるようにする方法です。切り花や葉を「枯れさせる」のではなく、「美しく乾かす」ことで、形や色合いの変化を味わうことができます。
ドライ化の魅力
-
✅ 長く楽しめる:1週間でしおれてしまう花も、数か月〜1年近く飾れます。
-
✅ 違った表情が出る:乾燥によって色が深まり、質感が変わります。
-
✅ 失敗しても味になる:折れたり色落ちしても、味わいに見えることがあります。
育てた植物を乾かして活かすメリット
家庭で育てたいけばな向け植物を、ドライ化して活かすことで、さらに植物との関係が深まります。
ドライ化向き植物が多い!
-
🌾フジバカマ、シュウメイギク、ミソハギなど、宿根草や秋草はドライにしやすい
-
🍂ヤナギやドウダンツツジなどの枝ものも、美しく乾きます
-
🌸ハーブ(ラベンダー、ローズマリー)やグラス類も、香りや形を残せます
「収穫→生ける→ドライ」まで楽しめる!
育てた植物の命をできるだけ長く楽しみたい――その気持ちに寄り添ってくれるのが、ドライ化です。作品としてのいけばなを終えたあとも、ドライの素材として活躍させることで、新たな表現が生まれます。
よく使う植物乾燥のテクニック3選
① 逆さ吊り乾燥(ハンギング法)
もっとも簡単で基本的な方法です。
手順:
-
花や葉を束にする(1本ずつでもOK)
-
茎の根元をゴムや紐で軽く結ぶ
-
風通しのよい日陰に逆さに吊るす(直射日光NG)
-
1〜2週間で完成
ポイント:
-
乾燥中に形が崩れないよう、余計な葉は取り除いておく
-
茎の太さや湿度によって、乾燥時間が変わる
② グリセリン法(柔らかく仕上げたいとき)
グリセリン液を吸わせて、しなやかさを残す方法です。
手順:
-
水:グリセリン=2:1の溶液を作る
-
茎を斜めに切って、液に浸ける
-
1週間ほど吸わせてから乾かす
向いている植物:
-
ドウダンツツジ、ユーカリ、アジサイなどの枝葉類
注意点:
-
色が濃く変色することがあります(それも味ですが)
③ 自然放置乾燥(いけばなの“余韻”として)
いけばな作品をそのまま花器に活けて、徐々に乾かす方法。
メリット:
-
形を保ったまま自然にドライ化できる
-
活けたまま変化していく姿を楽しめる
向いているケース:
-
ススキや枝もの、秋の草花(フジバカマ、ワレモコウなど)
ドライ化した植物の活かし方|いけばな×ドライの新しい提案
ドライ花材を加えたいけばな作品
生花とドライを組み合わせることで、季節のグラデーションや空気感を演出できます。
例:
-
フレッシュなリンドウ×ドライのミソハギ
-
生きた枝葉×ドライ化したススキの穂
オブジェ風の一輪挿し
茎が短くなっても、ガラス瓶や竹筒に挿すだけで「静物作品」のような趣に。
例:
-
ドライ化したローズマリーの穂を一本だけ活ける
-
シュウメイギクの茎をあえて曲げて活ける
壁掛け・スワッグ風のアレンジ
乾いた草花を束ねて、自然風の壁飾りに。
例:
-
ラフィアや麻紐で束ねるだけでナチュラルな雰囲気
-
色あせた実ものや葉のくすみも美しく映えます
私の体験談|「枯れる」という美しさを受け入れる
ある秋の日、庭で育てたフジバカマをいけたあと、そのままにしていたら、数日でやさしく乾き、色がすこし深まっていました。その姿に、「このまま、もう一度活けてみようかな」と思い立ち、次の日に別の枝とあわせていけてみたところ、なんとも言えない落ち着きのある作品になったのです。
いけばな=“生きているものだけ”と思っていたころから、だんだんと「いのちの終わりにも美しさがある」と気づくようになりました。
ドライ化しやすい植物10選|いけばなにも使える素材たち
| 植物名 | 特徴・見た目 | ドライ化のポイント |
|---|---|---|
| フジバカマ | 細い茎に小さな淡紅色の花が密集 | 風通しの良い場所で逆さ吊り。色がほんのり残る |
| ワレモコウ | 黒紅色の丸い穂状の小花 | 自然乾燥で形・色ともに風情が出る |
| ミソハギ | 細長い茎に小花が密に咲く | 花の形が崩れにくく、全体がまとまりやすい |
| ススキ | 白銀色の穂が特徴的 | 逆さ吊りで乾かすと、穂がふんわり仕上がる |
| ローズマリー | 細い茎と針葉、花も楽しめるハーブ | 香りが持続し、ドライにしても清潔感あり |
| ラベンダー | 紫色の小花と強い芳香 | 香りが長く残り、スワッグにも人気 |
| アジサイ | 丸く大きな花房 | グリセリン法で色持ちが良くなり、華やかさを保てる |
| ドウダンツツジ | 細かく分かれた枝と小さな葉 | 枝姿をそのまま活かして自然乾燥。冬場は赤く色づくことも |
| ユーカリ | 丸い葉と銀緑の色味 | 香りと形がそのまま残り、葉が落ちにくい |
| シュウメイギク | 秋に咲く繊細な花と細く長い茎 | 乾燥で花びらが薄く透け、趣のある質感に変化 |
ドライ化の失敗談と対策|“枯らす”を“活かす”に変えるヒント
ドライフラワーは気軽に始められる一方で、思わぬ失敗が起きることもあります。私自身、最初は何度も「思ったのと違う……」とがっかりしたことがありました。
でも、失敗には必ず「原因」と「解決策」があるもの。ここでは、実際にあった失敗例と、その後どう工夫したかをご紹介します。
失敗①|カビが生えた!部屋の隅で吊るしていたのに…
ある秋の日、フジバカマを逆さ吊りにしていたところ、2日目には茎の根元に白いふわふわが…。
原因
-
湿度が高く、空気がこもっていた
-
茎に余分な葉が残っていた
対策
-
必ず風通しの良い、直射日光の当たらない場所で乾燥させる
-
余分な葉は乾燥前に取り除く
-
除湿機や扇風機を使うと成功率が格段にアップ
失敗②|せっかくの花が、しぼんで黒ずんでしまった…
ラベンダーを干したはずが、香りも飛び、花も黒ずんでしまって台無しに。
原因
-
直射日光に当てすぎてしまった
-
高温で一気に乾かそうとした
対策
-
乾燥は“明るい日陰”が基本
-
じっくり1〜2週間かけて乾かすと、色や香りが長持ちする
-
エアコンの風が直接当たる場所は避ける
失敗③|茎がポキっと折れて活けられなかった…
ススキの穂を飾ろうとしたら、茎の途中でポキン。姿が崩れてしまいました。
原因
-
乾燥後に無理な角度で立てようとした
-
あらかじめ“形を整えて”干していなかった
対策
-
乾かす前に活ける姿をイメージして形を整えておく
-
支柱や紙筒を使って真っすぐ吊るす
-
折れた場合も、短く切って小瓶に活けるなど工夫次第で再利用可
失敗④|グリセリン処理したのにベタついて失敗…
アジサイの枝をグリセリン液に入れたら、ヌルッとベタついて失敗。色も濁ってしまった。
原因
-
液の濃度が高すぎた
-
浸けすぎて吸い上げすぎた
対策
-
グリセリン:水=1:2の薄めの割合から試す
-
茎の下1〜2cmだけを浸け、様子を見る
-
時間は1〜2日で十分。色が変わりすぎたら水洗いして自然乾燥に切り替え
失敗⑤|部屋に干していたら、家族に「ホコリ?」と言われた…
ドウダンツツジのドライをさりげなく飾ったら、家族に「掃除忘れてるの?」と勘違いされてしまいました。
原因
-
花材の色や形が地味になりすぎていた
-
飾り方に「意図」が見えにくかった
対策
-
1〜2種の素材を「まとめて飾る」ことで作品感が出る
-
瓶や花器を工夫して“飾る意識”を見せる
-
他のグリーンや流木と組み合わせても◎
失敗から生まれる、“あなたらしい乾いた美”のかたち
乾かして楽しむ技法は、失敗を重ねるほどコツが身につきます。うまく乾かせなかった花も、短く切って添え花にしたり、重ねて束ねたりすれば、いけばなの一部として生まれ変わります。
「完璧に仕上げる」のではなく、植物が乾いていく“ありのままの姿”を活かすのもまた、ドライならではの楽しみ方。
まずはひとつ、庭の草花を吊るしてみることから始めてみませんか?
四季を彩るドライ素材のいけばな活用法|四季の“余韻”を飾る楽しみ
ドライフラワーは、花が終わったあとも季節の記憶を部屋に残してくれる素材です。いけばなで使った植物をそのまま乾かしてもよし、意図的に“乾きゆく美”を取り入れてもよし。
ここでは、季節ごとのおすすめ花材と飾り方のヒントを紹介します。
🌸 春|やわらかな芽吹きの余韻をドライで残す
おすすめ花材
-
ミモザ:鮮やかな黄色とふわふわの花房
-
ユーカリ:丸葉と香りが持続
-
スイートピー:薄く透ける花びらが乾くとアンティーク調に
-
ビオラ・パンジー:押し花にしても可愛い
活用のヒント
-
グラスベースに1〜2本だけ挿すと、春らしい軽やかさが表現できる
-
ミモザは小さなリースにしても映える
-
いけばなの「花がら」としてさりげなく添えるのも◎
ワンポイント
フレッシュな花材との組み合わせで「春から初夏への移ろい」を表現してみましょう。
☀ 夏|香りと涼感をドライで楽しむ
おすすめ花材
-
ラベンダー:紫の花穂と豊かな芳香
-
ミント:清涼感ある葉と香り
-
スモークツリー:もこもこの質感が魅力
-
ローズマリー:細い葉が作品に軽さを与える
活用のヒント
-
涼しげなガラス花器や白磁の器に活けて、空間に「清涼感」を演出
-
ラベンダーやミントは吊るして香りのインテリアにも
-
スモークツリーは生花のユリやリンドウと組み合わせても相性◎
ワンポイント
暑さで植物が持たない時期だからこそ、“乾いた美しさ”を逆手に取る活け方を試してみては。
🍁 秋|色づく自然をそのまま閉じ込める
おすすめ花材
-
フジバカマ:乾いても色が残る秋の風情
-
ワレモコウ:黒紅の穂が作品を引き締める
-
ミソハギ:穂状の花が崩れにくい
-
ノイバラの実:赤い実が彩りに
-
ススキ:ふわりとした穂が風情を演出
活用のヒント
-
陶器や竹の器と合わせて、和のニュアンスを引き立てる
-
赤や紫、茶などくすみカラーのドライ素材でまとめると、深みのある作品に
-
実ものは束ねてスワッグにしても美しく長持ち
ワンポイント
秋はいけばなとドライの“境界”がもっとも自然に混じり合う季節。ぜひ、作品の中に「枯れゆく美」を意識的に取り入れて。
❄ 冬|静寂と温もりをドライで演出する
おすすめ花材
-
ドウダンツツジ:乾くと赤茶色になり、静かな雰囲気に
-
ネズの実:青みがかった実がアクセントに
-
アジサイ(グリセリン処理):ふっくらした質感と色合いを維持
-
ユーカリ(銀世界風):寒色系の葉で冬の冷たさを表現
活用のヒント
-
ガラスドームや深い器で静かな冬の室礼に
-
ドライの枝ものに金銀の水引や布飾りを添えて、迎春花にも応用可
-
殺風景になりがちな冬の部屋に、静けさと奥行きを加える花材として
ワンポイント
花の少ない冬だからこそ、「乾いた美」を主役に。**空間を静かに引き締める“余白の表現”**を楽しみましょう。
季節を「乾かして残す」という発想
いけばなは、生きた植物を使う芸術です。けれど、その命の終わりや、枯れていく姿にも美しさがある――それに気づくと、いけばなとドライフラワーの境界がゆるやかにつながっていきます。
季節が過ぎても、その名残を部屋に留めておけるドライ花材。ぜひ、“乾いた季節感”を活けるという新しい視点を、日々の中に取り入れてみてください。
よくある質問Q&A|初心者でもできる?
Q. ドライ化って初心者でもできますか?
A. はい。逆さ吊り乾燥から始めるのがおすすめです。難しい道具や薬品は不要で、自然乾燥でも十分美しい仕上がりになります。
Q. 色がくすむのが心配ですが?
A. ドライ化は色が変わるのも魅力の一つです。あえてくすんだ美しさを活かす活け方を考えてみましょう。
Q. どんな植物でもドライにできますか?
A. 水分の多い植物(チューリップ、ヒマワリなど)は難しいですが、細身の枝や草花、穂ものは比較的成功しやすいです。
コラム|私のドライ化実験記|フジバカマと秋の午後
庭の隅に、毎年そっと咲いてくれるフジバカマがあります。いけばなで活けると、どこか儚げで、秋の空気そのものを切り取ったような風情が好きで、私はこの草花にずっと惹かれてきました。
ある年、いつもなら活け終わったあとに処分してしまう茎を、なんとなく捨てるのが惜しくなって――思い立ったように、束ねて吊るしてみることにしました。
物干しの陰、風が通る場所。特に道具も使わず、ただ輪ゴムでまとめてぶら下げただけでした。
数日経って様子を見ると、フジバカマは花びらが少し縮みながらも、全体の姿をそのまま保っていました。色も思ったより残っていて、どこかセピア色の写真のような雰囲気。
そのドライになったフジバカマを、小さな陶器の花器にそっと挿してみると、これがなんとも味わい深い。
生花とは違う、時間の積み重なりを感じさせる静けさ。香りこそないけれど、そこに「秋の午後」のような空気が、確かに漂っている気がしたのです。
それ以来、「静かに変化していくものを、そのまま飾る」ということに、抵抗がなくなりました。むしろ、“今の姿”を活けるといういけばなの本質に、少し近づけたような気がしています。
まとめ|いけばなと“乾いた花材”、そのあわいを楽しもう
育てた植物をドライ化して活かすことで、いけばなの表現がさらに広がります。フレッシュな姿から、時間を重ねていく変化、そしてドライとなったあとまで――そのすべてを「美」として受け取ることで、植物との関係はより豊かになります。
ぜひ、いけばなの延長としての“ドライの美”を、暮らしの中で楽しんでみてください。