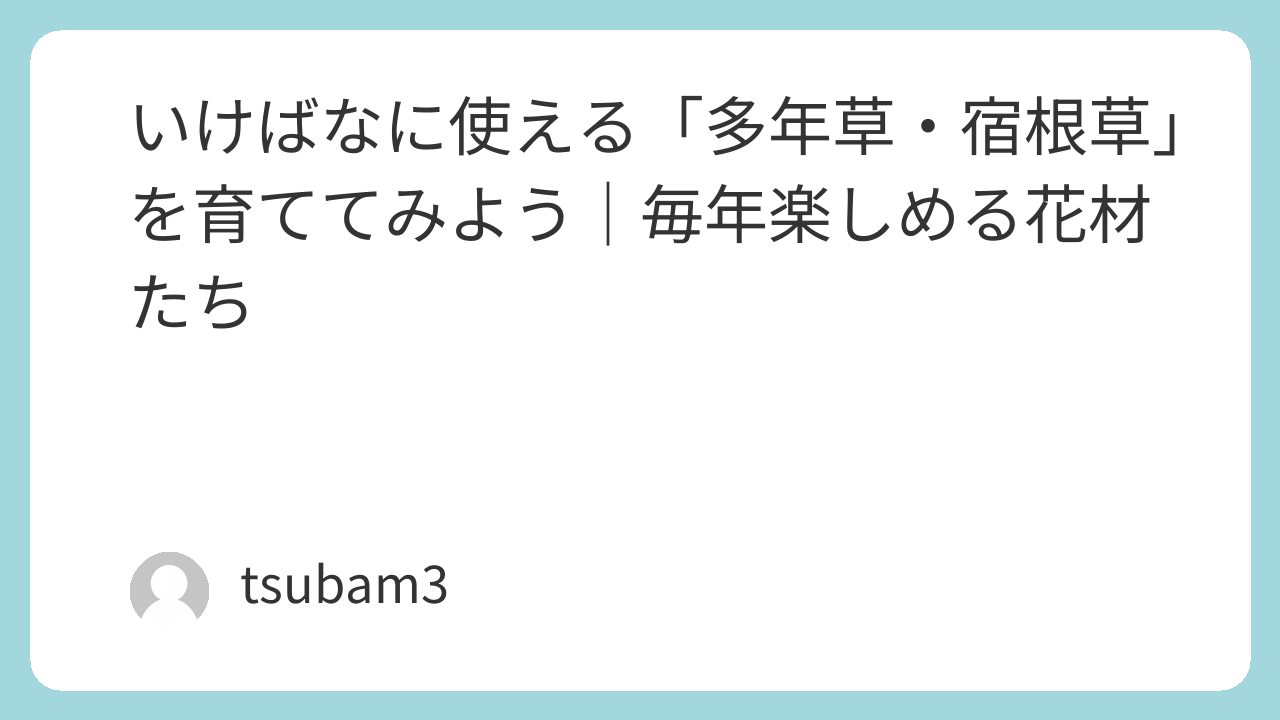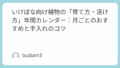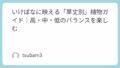はじめに|繰り返し楽しめる植物との暮らし
一年草はその年かぎりの華やかさがありますが、何年にもわたって育ち続ける「多年草・宿根草」は、いけばなを続けていく上でとても頼りになる存在です。
私自身、フジバカマやシュウメイギクなどを毎年庭で育てながら、「今年も咲いてくれた」と嬉しくなります。 植物とともに季節を重ねていく感覚は、いけばなの美意識にも通じていると感じています。
この記事では、いけばなに使いやすい多年草・宿根草を中心に、その魅力や育て方、活け方のポイントをご紹介します。
🔍 基本解説|多年草・宿根草とは?
まずは「多年草」と「宿根草」の違いを簡単に整理しておきましょう。
- 多年草(たねんそう):一年を通して地上部が枯れず、葉や茎が残るタイプ。たとえばクリスマスローズなどは常緑性多年草です。
- 宿根草(しゅっこんそう):冬には地上部が枯れますが、根が生きており春になると再び芽吹く植物。代表例にフジバカマやシュウメイギクがあります。
一般的なガーデニングではこの2つをあまり厳密に区別しない場合が多く、本記事でもまとめて「多年草・宿根草」として紹介します。
🌸 おすすめ7選|いけばなに使いやすい多年草・宿根草
ここでは、いけばなに使いやすく、育てやすい多年草・宿根草をピックアップしてご紹介します。
| 植物名 | 花期 | 特徴 | 活け方のコツ | 育てやすさ |
|---|---|---|---|---|
| フジバカマ | 秋 | 和の趣・淡い香り | 葉をすっきり整理して品よく | ◎ 初心者向け |
| シュウメイギク | 秋 | 優雅な花姿・長持ち | 茎を斜めに活けて動きを出す | ◎ |
| クリスマスローズ | 冬〜春 | 落ち着いた雰囲気・花期が長い | 花首を短めにカットして活ける | △ やや中級 |
| カンパニュラ | 春〜夏 | 鐘型の花が可憐 | 直立したラインを活かして | ◎ |
| アスチルベ | 初夏 | フワッとした穂状の花 | 空間にボリュームを加える | ◎ |
| ヒメヒオウギズイセン | 夏 | 鮮やかな朱色・細長い茎 | しなやかな曲線を引き立てて構成する | ○ |
| ツワブキ | 秋〜冬 | 花も葉も使える・丈夫 | 光沢のある葉を主役に構成 | ◎ |
🌿 育て方のコツ|日当たり・水やり・手入れの基本
多年草・宿根草は、一度植えると長く楽しめる半面、環境によって生育が左右されやすい面もあります。以下に育てる際の基本をまとめました。
日当たりと植える場所
半日陰〜明るい日陰を好む品種が多く、庭の北側や建物の影などでも育ちます。特に夏の直射日光が苦手な植物には、風通しのよい日陰が適しています。逆に、アスチルベのように明るさを好む種類は、午前中だけ日が差すような東向きの場所が理想的です。
地植えでも鉢植えでもOKですが、大きく育つものは地植え向き。鉢植えにする場合は、鉢のサイズを1〜2年ごとに見直し、根詰まりを防ぎましょう。
水やりと土の管理
適度な湿度が必要。乾燥しすぎないよう注意。とくに新芽が出る春先や夏場の乾燥期には、朝晩の水やりを習慣にすることで、元気な株を育てやすくなります。
腐葉土などを混ぜた水はけのよい土が理想です。市販の草花用培養土に赤玉土やくん炭を混ぜると、通気性・保水性ともにバランスがとれます。
肥料と手入れ
春と秋に緩効性肥料を与えると元気な株に育ちます。追肥は控えめに、肥料過多になると葉ばかり茂って花が咲かなくなることもあるので注意が必要です。
花後の剪定や、数年に一度の株分けが長持ちのコツです。剪定の際は、葉のつけ根で切ると次の芽が育ちやすくなり、全体の姿も整いやすくなります。
さらに、春〜初夏にはアブラムシやナメクジなどの害虫が発生しやすくなるため、毎日の観察も大切です。異変に気づいたら早めに駆除することで、健康な花材を育てることができます。
害虫・病気の予防
多年草・宿根草は比較的病害虫に強い傾向がありますが、油断は禁物です。特に春から初夏にかけては、アブラムシやナメクジ、ハダニなどがつきやすくなります。
葉が縮れていたり、茎がベタついていたりする場合は害虫の可能性があるので、早めに駆除や対策を行いましょう。無農薬で管理したい場合は、木酢液の散布や、ていねいな手入れによる予防が効果的です。
観察する習慣を
植物は言葉を発しませんが、毎日見ていると「ちょっと元気がないかも?」といった変化に気づけるようになります。葉の色、つぼみのふくらみ、茎の伸び具合などをチェックする“観察の目”を養うことで、トラブルの早期発見や、開花のベストタイミングを逃さずに済みます。
✨ 活け方のヒント|多年草・宿根草をいけばなに活かす
多年草・宿根草は、いけばなにおいて以下のような魅力があります。
- 花以外の部分が使える:葉・つぼみ・実など、脇役にもなる素材が豊富。
- 姿に変化がある:つぼみから満開、枯れ姿まで、それぞれに美しさが。
- 長持ちしやすい:花期が長く、切り花にしても比較的日持ちが良い。
稽古用としても便利で使い勝手がよく、季節感や風情を映し出す素材としても重宝します。
多年草・宿根草を取り入れるコツ
毎年使える多年草・宿根草は、自宅に“いけばなの素材庫”を持っているようなもの。いけばなを日常的に楽しむために、育てておくと便利です。
✅自然と四季を感じられる:咲き始めの芽吹き、つぼみのふくらみなども楽しめます。
✅鉢植えで手軽に:ベランダでも育てられる品種多数。鉢から直接切って活けられるのも魅力。
✅咲きそろったタイミングで一気に活ける:同じ株から異なる素材(葉・茎・花)が得られるため、一作品にまとまりが生まれます。
📅 季節別アレンジ|春夏秋冬の活用例
いけばなにおいて、季節感はとても大切な要素です。同じ多年草・宿根草でも、季節ごとの植物を意識して活けることで、作品に深みと自然の流れを与えることができます。
🌸春|芽吹きとやさしさを表現
- カンパニュラの可憐な鐘型の花を主役に、アジュガの低い葉ものを合わせて春の訪れを表現。
- クリスマスローズは晩冬から早春に咲き始めるため、冬から春への橋渡しにぴったり。
☀ 夏|清涼感と力強さを演出
- 暑い季節には、アスチルベのふわふわした穂や、ヒメヒオウギズイセンの鮮やかな茎を添えて構成し、動きと涼しさを演出。
- 明るい葉もの(例:ギボウシ)を取り入れると、清涼感が一段と高まります。
🍁秋|しっとりとした情緒を活ける
- フジバカマやシュウメイギクは、秋の空気にぴったりな落ち着きと余韻さを持つ花材。
- 茎の曲がりや葉の黄変も、自然な季節感として活けることができます。
❄ 冬|凛とした張りつめた空気感と余白の美
- 花が少ない時期は、ツワブキの光沢のある葉と黄色い花で凛とした佇まい存在感を演出。
- 葉のみや、冬芽を活ける“間”の表現もおすすめ。
このように、季節を意識しながら多年草・宿根草を活けることで、より自然と調和したいけばな表現が可能になります。
🌱 増やし方ガイド|株分け・挿し芽で花材を育てよう
多年草・宿根草の魅力のひとつは、「増やすことができる」という点です。いけばなに使う花材を自分で増やしていけたら、経済的で環境にもやさしく、何より育てる喜びがぐんと広がります。
株分けの基本とタイミング
株分けとは、大きく育った株を数株に分けて再び植え直す方法です。株が混み合ってきたり、花つきが悪くなったときは、更新を兼ねて株分けすると植物が元気を取り戻します。
- おすすめ時期:春(3〜4月)または秋(9〜10月)
- やり方の例:フジバカマやシュウメイギクは根を掘り上げ、芽のついた部分を分けて植え直します。
株分けしたものは、自宅の別の場所に植えるだけでなく、鉢にして知人にプレゼントしたり、いけばな仲間と交換するのも素敵な活用法です。
挿し芽で手軽に増やす
種類によっては「挿し芽(さしめ)」で簡単に増やすことも可能です。茎をカットして土に挿しておくと、根が出て新しい株になります。
- アスチルベやカンパニュラなどは挿し芽で増やしやすい代表格。
- 湿度を保つためにビニール袋などでカバーすると成功率がアップします。
増やした株をどう活ける?
育てたばかりの若い株は小ぶりな姿が多く、主役というよりも「添えの花材」にぴったり。逆に、数年たって立派に育った株は、枝ぶりや葉のボリュームも増し、堂々と主役として活けられるようになります。
株分けや挿し芽で得た新しい花材を使えば、作品に育てた時間が作品にそっとにじみ出ます。いけばなと園芸がつながる瞬間は、まるで作品に命を託すような感覚があります。
「増やすことで活ける幅も広がる」――それが、多年草・宿根草の大きな魅力のひとつです。
よくある質問Q&A
Q. 毎年咲かない年もあるのはなぜ?
A. 株が若すぎたり、根詰まり・肥料不足が原因のことも。株分けや施肥で改善可能です。
Q. 鉢植えでも育てられますか?
A. 多くの多年草・宿根草は鉢植えでも育ちます。乾燥に注意しながら管理しましょう。
Q. 宿根草は冬に枯れてしまうけど大丈夫?
A. 地上部が枯れても、根が生きています。春になるとまた芽吹くので心配いりません。
Q. どの季節にどの多年草を活けたらよいか、迷ってしまいます。
A. 季節ごとのおすすめ活用例を参考に、「今」咲いているものや葉の色づき具合で選んでみましょう。植物の“今の姿”を活かすことが、いけばなの自然な表現につながります。
いけばな教室での活用事例&講師の声
多年草・宿根草は、いけばな教室の現場でも少しずつ注目されてきています。花材費を抑えつつ、季節感や自然らしさを作品に取り入れられるという点が評価されています。
生徒さんの実例から
ある教室では、庭に咲いたアスチルベを持参して稽古に使った生徒さんがいました。その穂状の花の柔らかさと自然な揺らぎが好評で、講師からも「ご自宅でここまで立派に育てたのはすごいですね」と感嘆の声が上がったそうです。
また、クリスマスローズを鉢で育てている方は、冬から春にかけての貴重な花材として活用し、「切り花よりも活ける意欲がわく」と話していました。
講師の視点から
多くの講師が共通して語るのは、「自分の手で管理してきた植物を活けると、気持ちの入り方が違う」ということ。いけばなは単なる装飾ではなく、“自然との対話”であり、その入り口として自家栽培の花材はとても有効なのです。
ある中堅の講師は、「株分けしたフジバカマを教室で共有し、皆で活けてみたら、一本一本の茎に込められた気持ちが作品ににじみ出ていた」と語ります。
教室で取り入れるための工夫
- 鉢植えの状態で持参し、その場で切って活けるスタイル
- 花材のシェア会(余った株の交換)
- 年に一度の「自分で育てた花材だけで活ける日」など
こうした取り組みにより、生徒のモチベーションが高まり、いけばなと植物の関係性をより深く体感できるようになります。
多年草・宿根草は、“教わる”いけばなから“手をかけて創る”いけばなへ――そんな学びの広がりを支えてくれる存在でもあるのです。
🪴 体験コラム|“花材畑”を作って見えた世界
ここでは、私自身が実際に多年草・宿根草を育ててみて感じた、リアルな体験を少しご紹介したいと思います。
数年前、いけばなの稽古を続ける中で、「毎回花材を買うのは大変だな」と思ったことがきっかけでした。そんなとき、庭の隅にあったフジバカマの小さな芽を見つけ、「これ、活けられるかも」とふと思いついたのです。
それが、私の“花材畑づくり”のはじまりでした。最初はプランターに数株、クリスマスローズやアスチルベを植える程度でしたが、気がつけば庭の一角が「いけばなゾーン」になっていました。
春にはカンパニュラ、初夏にはアスチルベ、秋にはシュウメイギクやツワブキ……季節ごとに表情を変える植物たちを見ていると、「次はどんなふうに活けようか」と自然と創作意欲がわいてきます。
なにより、植物と向き合う時間が増えたことで、いけばな作品に対する視点も変わりました。単に“花を活ける”だけでなく、“育てた命をどう活かすか”という視点が生まれたのです。
もちろん、育てる中ではうまく咲かなかった年もありますし、虫に葉を食べられたこともあります。それでも、毎年少しずつ変化していく庭の風景と向き合う時間は、いけばなと同じくらい尊いものになっています。
“花材畑”は、技術よりも気持ちで作るもの。失敗しても、また来年。その繰り返しが、いけばなをもっと身近に、もっと豊かにしてくれました。
これからも私は、庭に咲いた花を一本手にとって、今日の気持ちをそのままに花器に託したいと思います。
まとめ|手間なく四季を活けるために
いけばなを長く楽しむには、身近に使える花材を持っておくことが大きな助けになります。多年草・宿根草は、育てる楽しさと活ける楽しさを同時に与えてくれる存在です。
「今年も咲いた」「この花、去年も活けたなあ」――そんなふうに植物との関係が深まっていくのは、いけばなならではの喜びかもしれません。
ぜひ、あなただけの“花材の庭”を少しずつ作ってみてください。まずは一株、庭に迎えてみませんか?