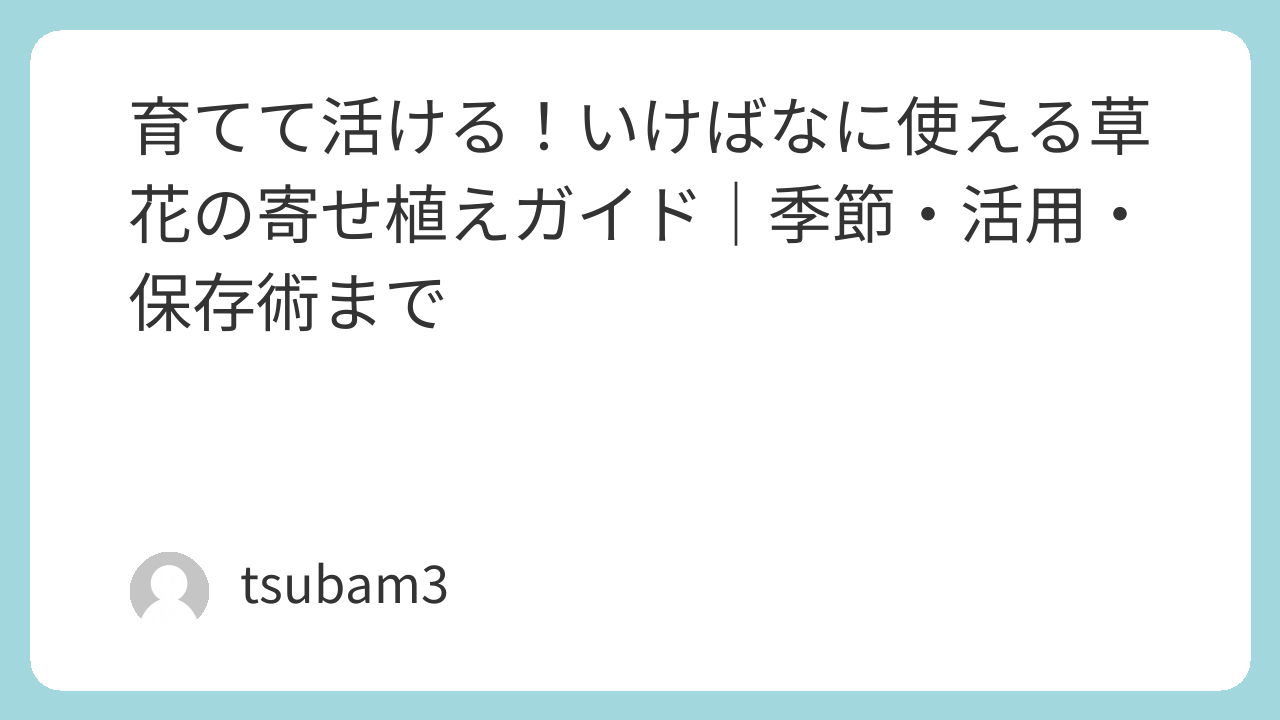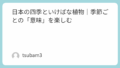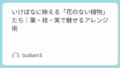はじめに|寄せ植えは“育てる+活ける”の宝箱
いけばなを日常に取り入れたいと思ったとき、ふと悩むのが「花材をどう揃えるか」ということ。そんなとき、私が頼りにしているのが「草花の寄せ植え」です。
寄せ植えは、複数の植物をひとつの鉢やプランターで育てるスタイル。草丈・葉の形・花色などが自然に混ざり合い、育てるだけで美しい“素材の箱庭”が完成します。
この記事では、寄せ植えからいけばなに展開する楽しみ方を、私自身の体験も交えながらご紹介します。
寄せ植えの魅力とは?
育てながら“使いどき”を見極められる
寄せ植えの良さは、日々の変化を身近に感じられること。つぼみが膨らんできた、草丈が伸びてきた――そんな瞬間に、「今が活けどきだな」と気づくことができます。
少ないスペースで多彩な植物を楽しめる
庭がなくても、ベランダや玄関先に一鉢あればOK。鉢ひとつで3~5種の植物を楽しめるのも魅力です。
自然な組み合わせが、そのまま“作品”になる
寄せ植えの配置は、いけばなの構成にも活かせます。高低差や色のバランスを意識して育てれば、切り取るだけで自然な作品構成が整います。
いけばな向き「草花寄せ植え」おすすめの組み合わせ
| 組み合わせ例 | 特徴 | 季節 |
|---|---|---|
| ナデシコ+アイビー+ローズマリー | 花・葉・香りのバランス◎ | 春〜初夏 |
| ミヤコワスレ+リュウノヒゲ+ヒメツルソバ | 和風・やわらかい印象 | 初夏〜秋 |
| フジバカマ+タイム+アジュガ | すっと立つ線+低く広がる足元 | 秋 |
| ツワブキ+ヤブラン+ユリオプスデージー | 葉の形と色の変化で魅せる | 秋〜冬 |
育て方のポイント|寄せ植えだからこその工夫
1. 同じ環境で育つ植物を組み合わせる
-
日照条件(水が好きな植物×乾燥に強い植物などは避ける)
-
草丈・生長スピードをそろえると管理が楽
2. 間引きと剪定を活ける練習に活かす
-
生長して混み合ってきたら、切り戻し=いけばなの花材収穫と捉えて活用
-
小さな一枝でも「副枝・添え枝」に使える
3. 季節ごとに一部を入れ替える
-
一年草と多年草を組み合わせておくと、花が終わっても入れ替えが簡単
-
たとえば、春にパンジー→初夏にペチュニアなど
いけばなに展開するときのコツ
寄せ植えの「配置」をヒントに構成を考える
-
高い植物を主枝に、低い植物を足元に
-
アイビーやリュウノヒゲの“動き”を流れとして活かす
切り取る位置は、バランスより“表情”重視で
-
長さにとらわれず、「この一枝、表情があるな」と思う部分を選ぶ
-
茎の曲がりや葉の向きもいけばなの見どころに
残した鉢も“次の育成”に生かせる
-
使わなかった部分も育ち続けるので、また次回の花材候補に
-
いけばなと園芸の循環が自然に生まれる
寄せ植えスタイル別|いけばなに活かしやすいレイアウトとは?
寄せ植えといえば「彩りがきれい」「形がまとまっている」といった見た目の印象が重視されがちですが、いけばなに活かす場合には、**構成(レイアウト)**が大きなカギになります。
ここでは、寄せ植えの主なレイアウトを4つに分類し、それぞれがいけばなにどう活かせるかをご紹介します。
1. 放射型レイアウト(ドーム型)
鉢の中心に背の高い植物を植え、外側に向かって低い草花を放射状に配置するスタイル。よく市販の寄せ植えにも見られる基本形です。
いけばなでの活用:
-
中央の高い植物が「主枝」、外側の草が「副枝」や「添え枝」として使える
-
自然な高低差がすでに作られており、切り取るだけで構成しやすい
例: サルビア+アリッサム+アイビーの組み合わせ
2. リズム型レイアウト(非対称・動きあり)
草丈や葉の広がりをあえてアンバランスに配置し、躍動感や自然な動きを楽しむスタイル。草花の個性を活かすのに適しています。
いけばなでの活用:
-
茎の曲がりや斜めの成長がそのまま“動き”となって生かせる
-
一見不揃いな形こそ、いけばな向き
例: ガウラ+カレックス+ハーブ類などの組み合わせ
3. 密集型レイアウト(モコモコ系)
高さや広がりよりも「密度」重視でぎっしり詰めて植えたスタイル。見た目は華やかで人気ですが、いけばなへの活用には工夫が必要です。
いけばなでの活用:
-
草花の間引き・切り戻しの際に、形の良い部分だけ選ぶのがコツ
-
“群生の一枝”として、ミニマムに活けるスタイルに向く
例: パンジー+アリッサム+ヒューケラの冬〜春寄せ植え
4. ナチュラル型レイアウト(自然風)
草丈や配置にあえて手を加えすぎず、植物の“なりゆき”に任せた自然風レイアウト。野草や宿根草と相性がよく、管理もしやすい。
いけばなでの活用:
-
ありのままの姿を生かすことで、表情豊かな作品に
-
自然な曲がり・伸び方が魅力になり、剪定の手間も少ない
例: フジバカマ+アジュガ+ワイヤープランツの秋〜初冬寄せ植え
寄せ植えのレイアウトを意識することで、「どの部分をどのように活けるか」のヒントが自然と見えてきます。いけばなを意識して寄せ植えを作れば、育てながら構成をシミュレーションできるようになり、作品づくりがよりスムーズになります。
実録レポート|私の寄せ植え→いけばな活用例3選
ここでは、私が実際に育てて活けた「寄せ植え→いけばな」活用例を3つご紹介します。鉢植えからどんな植物を選び、どのように活けたかを具体的にお見せすることで、みなさんの参考になれば幸いです。
【🌸春】ナデシコ+アイビー+ローズマリーの寄せ植え
レイアウト: 放射型
いけばなで使った花材:
-
ナデシコの1本(控え枝)
-
アイビーの長く伸びた枝(副枝)
-
ローズマリーの直立茎(主枝)
活け方のポイント:
アイビーの伸び方に動きがあり、全体の“流れ”を決める構成要素になりました。香りのあるローズマリーが主軸になり、ナデシコが軽やかな添えに。
感想:
切り取った後も鉢はそのまま育ち続けるので、週ごとに少しずつ違う枝を使えるのが便利でした。
【☀夏】ペチュニア+コリウス+ミントの寄せ植え
レイアウト: リズム型
いけばなで使った花材:
-
ペチュニアの咲き始めの枝(主枝)
-
ミントの小枝(添え枝)
活け方のポイント:
ミントはあえて花をつける前に切り、葉の香りを活かして活けました。ペチュニアは咲きかけの柔らかな曲線を主役に据え、コリウスは残して次回用に。
感想:
ミントを活けると、ふとした瞬間に香りが漂って心がほどけるような感覚に。作品全体に“見えない気配”が加わった気がします。
【🍁秋】フジバカマ+タイム+アジュガの寄せ植え
レイアウト: ナチュラル型
いけばなで使った花材:
-
フジバカマのしなやかな枝(主枝)
-
タイムの小枝(添え枝)
活け方のポイント:
フジバカマの茎の曲がりと葉のつき方が、非常に表情豊かでそのまま主枝として活用。タイムはほんの一枝でも足元に“香りと余白”を添えてくれました。
感想:
多年草のフジバカマは毎年花材になってくれる“頼れる存在”。秋の作品には欠かせない寄せ植えメンバーです。
これらの体験を通じて感じたのは、「寄せ植えを作ると、いけばなの材料が目の前で育っていく喜びがある」ということ。毎日の水やりが、作品への準備に変わる……そんな感覚を、ぜひみなさんにも味わっていただきたいです。
一年中楽しむ寄せ植え×いけばな|季節別おすすめプラン
寄せ植えは、季節に合わせて花や葉の表情を変えながら、一年を通して楽しめるのが魅力です。そして、その中から旬の素材を切り取っていけばなに活かせば、季節感あふれる作品に仕上がります。
ここでは、春・夏・秋・冬それぞれにおすすめの寄せ植えプランを、実用的な組み合わせとともにご紹介します。
🌸 春|芽吹きと華やかさを楽しむ寄せ植え
おすすめ植物:
-
パンジー(彩り)
-
イベリス(白花で引き締め)
-
カモミール(香り+ナチュラル感)
いけばな活用ポイント:
パンジーはやわらかいラインのある枝を添えに。イベリスの白がアクセントになり、カモミールの香りは控えめながら印象的です。
☀ 夏|色と動きで魅せる寄せ植え
おすすめ植物:
-
ペチュニア(主役の花)
-
コリウス(色葉)
-
ローズマリー(香りと高さ)
いけばな活用ポイント:
コリウスの葉色を花の代わりに主役にすることも。ローズマリーは縦のラインを作るのに便利で、香りも楽しめます。
🍁 秋|深みのある色と質感を楽しむ寄せ植え
おすすめ植物:
-
フジバカマ(秋の風情)
-
リンドウ(青紫の落ち着いた花)
-
トウテイラン(シルバーリーフ)
いけばな活用ポイント:
フジバカマの自然な曲がりが作品の“流れ”をつくります。色を抑えた組み合わせで、落ち着きのある構成に。
❄ 冬|静けさと強さを感じる寄せ植え
おすすめ植物:
-
ツワブキ(常緑のつや葉)
-
ハボタン(冬の彩り)
-
ヤブコウジ(赤い実)
いけばな活用ポイント:
ツワブキの葉のツヤが静寂を、ハボタンが“花のような存在感”を演出。実もののヤブコウジで季節感を強調できます。
こうした季節ごとの寄せ植えをいくつか育てておくことで、切り取るだけで旬の花材が手に入る状態に。1年を通じていけばなを楽しむ、心強い味方になります。
寄せ植えで育てた植物を長く楽しむ保存術
せっかく育てたいけばな用の植物。切って活けたあとも、「もう一度楽しめたらいいのに」と思うことはありませんか?
ここでは、寄せ植えから切り取った植物を長く楽しむための3つの保存・再活用術をご紹介します。
1. ドライ化して“もう一度活ける”
乾燥に強い草花であれば、ドライフラワーとして再利用が可能です。
ドライにしやすい植物例:
-
ローズマリー
-
ラベンダー
-
ユーカリ
-
タイム
-
ミモザ(春限定)
ポイント:
-
風通しの良い日陰に逆さに吊るして乾燥させる
-
完全に乾いたら、いけばなやスワッグに再利用
👉 ドライにすることで「枯れゆく美しさ」を楽しめ、長く飾ることができます。
2. 挿し芽や株分けで“育て直す”
多年草や宿根草は、切ったあとに挿し芽や株分けで再生させることができます。
活用できる植物例:
-
アイビー(挿し芽)
-
ミント(挿し芽)
-
ツワブキ(株分け)
-
アジュガ(ランナー)
方法:
-
切り戻しのタイミングで、元気な枝を水差し・挿し木に
-
植え替え時に分けた株を新たな寄せ植えに利用
👉 一度育てた植物を“循環的に”楽しめる、いけばな×ガーデニングならではの利点です。
3. 水耕栽培やミニ鉢で再利用
細い枝や根付きのものは、水耕栽培で再生することもできます。
おすすめ植物:
-
バジル
-
ワイヤープランツ
-
リュウノヒゲ
やり方:
-
ガラス容器や空き瓶に水を張って、枝を数日間差しておく
-
根が出てきたら、再び鉢に植えて育て直し
👉 小さな容器に活けておけば、ミニいけばな風にも楽しめます。
切ったあとも、育てて活けて、また育てて――。寄せ植えは、そんな**“いけばなの循環”**を実現してくれる存在です。上手に保存・再利用しながら、長く植物と付き合っていきましょう。
いけばな教室でも活用できる!寄せ植え育成のすすめ
寄せ植えというと、自宅で楽しむものという印象が強いかもしれませんが、実はいけばな教室やグループ活動にこそ取り入れてほしい魅力があります。
ここでは、いけばな教室で寄せ植えを活用するメリットと、その実践アイデアをご紹介します。
教室で寄せ植えを育てるメリットとは?
1. 花材の準備がラクになる
毎週・毎月の教室で「今日は何の花材にしよう?」と悩むのは、指導側にとっても受講者側にとっても大変なこと。
あらかじめ教室で寄せ植えを数鉢育てておけば、その季節に応じた花材が自然に育ち、すぐ使えるようになります。
-
切ってそのまま使える
-
余った枝はまた育て直せる
-
花材費のコストも削減可能
2. 育てる過程も学びにつながる
いけばなは「切った素材を活ける」芸術ですが、植物がどのように成長し、花をつけ、枯れていくかを知ることで、より深い表現力が生まれます。
寄せ植えを育てることで、
-
季節ごとの植物の姿を観察できる
-
茎の伸び方・葉のつき方を自然に学べる
-
“使いどき”の判断力が身につく
という育成視点の学びが得られます。
3. 生徒同士の交流やイベントにも
「みんなで育てる鉢」や「一人一鉢の寄せ植え体験」は、教室の中に共同作業や会話のきっかけを生み出します。
-
季節ごとの植え替えワークショップ
-
寄せ植えから活ける「二段階の作品制作」
-
教室内のコンテストや展示会への発展も可能
実際に、私の知人のいけばな教室では、生徒同士で“推しの寄せ植え”を見せ合いながら、活けた作品を写真に撮って展示するという取り組みを行い、とても盛り上がったそうです。
教室での取り入れ方アイデア
| 活用シーン | 内容 |
|---|---|
| 月ごとの「育てる鉢」 | 季節の草花を寄せ植えし、育ててから活ける |
| 年間テーマ「四季の鉢」 | 春・夏・秋・冬の寄せ植えをそれぞれ用意し、作品に活用 |
| ミニ講座としての導入 | 植え方や管理方法を指導時間の一部に組み込む |
| 作品展示の素材に | 寄せ植え→いけばな→写真パネルや実物展示へ展開 |
教室で育てて活けるメリットとは?
いけばな教室で寄せ植えを取り入れることで、植物への理解が深まり、創作の幅も広がります。ただ切って活けるだけでなく、「育てる」という視点をもつことで、作品に込める気持ちや表現の深さが変わってくるのです。
教室全体で、あるいは小さなグループで寄せ植えに取り組んでみることで、いけばなの学びも暮らしも、より立体的で豊かなものになるでしょう。
よくある質問Q&A|寄せ植え×いけばな初心者にも安心!
Q. 土から抜かずにそのまま活けてもいいですか?
A. 基本は切って使いますが、小鉢や小盆栽のように「鉢ごと活ける」手法もあります。苔玉などを応用すると◎。
Q. 寄せ植えの植物が大きくなりすぎたら?
A. 一度植え替えて株分けを。分けたものをいけばなに活用するのもおすすめです。
Q. 寄せ植えのデザインに迷います…
A. まずは「草丈の違う3種」を選ぶとバランスが整いやすいです。色は同系色でまとめるか、アクセントで1色足すのも◎。
まとめ|「育てる+活ける」のよろこびを一鉢から
寄せ植えは、見た目に楽しいだけでなく、いけばなをもっと身近に、もっと自由に楽しめる素敵な方法です。
私自身も、日々の水やりのなかで「この枝、いい曲がりしてきたな」と思うことがよくあり、育てながら“作品の構想”が浮かんでくるのが嬉しい瞬間です。
ぜひみなさんも、自分だけの寄せ植えを作って、そこからいけばなの世界へと広げてみてください。