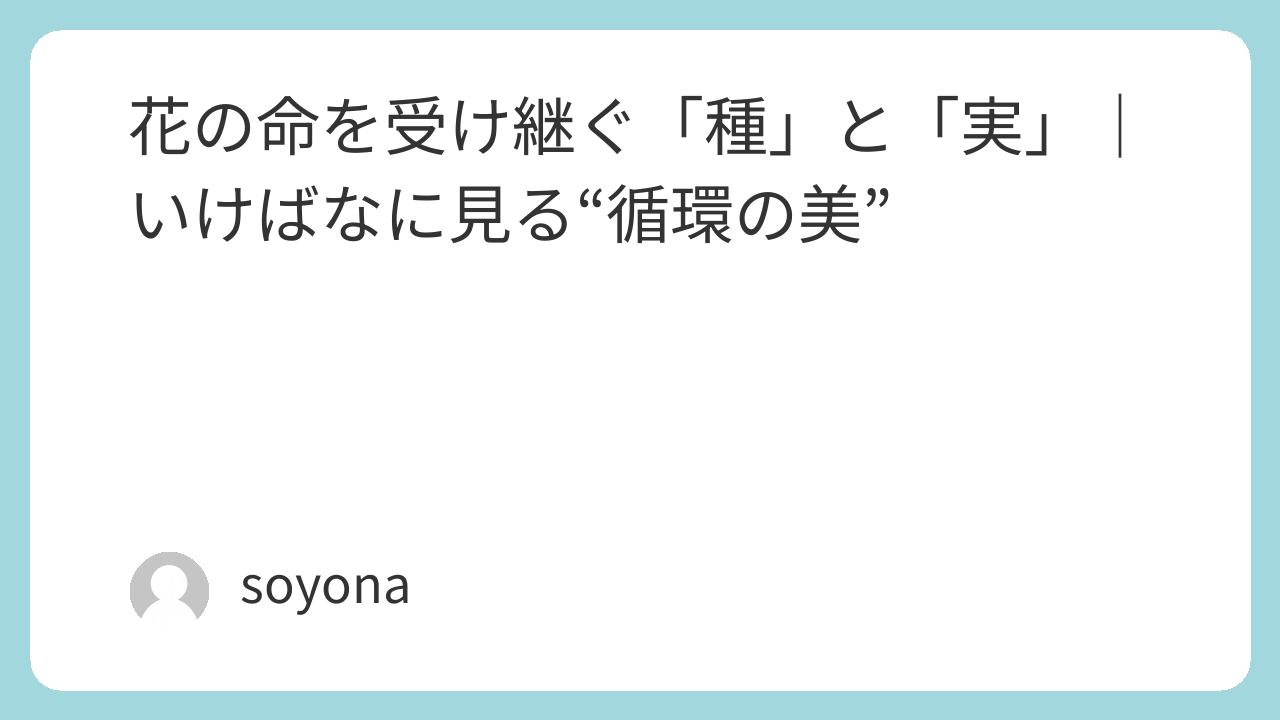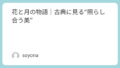花が咲き誇る季節が過ぎると、静かに姿を現すものがあります。それは「種」や「実」。
花の華やかな瞬間のあとに訪れるこの時間には、命の余韻と次の季節への約束が宿っています。
いけばなの世界でも、種や実を用いた表現は古くから大切にされてきました。
それは単なる飾りではなく、「命の循環」を象徴する“物語の余白”として生けられるのです。
種と実の象徴 ― 命がつながるかたち
花が咲くということは、やがて種が生まれるということ。
日本人はその当たり前の自然の流れの中に、深い美を見出してきました。
桜が散り、青い実をつけ、やがて来年の花を育むように――花は終わりであり、同時に始まりでもあります。
種や実は「再生」「継承」「希望」の象徴。
いけばなでは、落ちた種をそっと添えたり、熟した実を枝ごと活けたりして、
“時間の流れ”や“生命の循環”を表現します。
そこには、「今ここにある命は、次の命につながっている」という祈りのような感覚が宿っています。
いけばなに見る「実もの」の美学
秋から冬にかけて、いけばなの花材として人気なのが「実もの(みもの)」です。
南天(なんてん)・柊(ひいらぎ)・椿の実・柿・ツルウメモドキなど、
赤や橙の実が空間に温かみを添え、季節の深まりを伝えます。
これらの実は、単に「彩り」としてだけでなく、
「過ぎゆく季節の名残」「命の果実」「次の春への希望」として扱われます。
とくに南天は「難を転ずる」に通じる縁起物として、
正月のいけばなや茶花(ちゃばな)にもよく使われてきました。
代表的な“実もの”花材と意味
- 南天(なんてん):難を転ずる/魔除け/繁栄
- ツルウメモドキ:実り/家庭円満/秋の豊かさ
- 柿(かき):実り/感謝/秋の象徴
- 椿の実:静寂/内なる力/命の余韻
- 松ぼっくり:永続/希望/自然の記憶
実ものは、時間を経て色が変わるのも魅力のひとつ。
赤から深紅へ、黄から茶へと変化していく姿は、
まさに「移ろいの美」そのものです。
“命のリレー”を表すいけ方の工夫
いけばなで種や実を扱う際には、「主役」としてよりも「語り手」として添えることが多いです。
たとえば――
- 花が終わった枝に、実を少し残して活ける
- 散った花びらの横に、小さな種を添える
- 一輪の花と熟した実を対比させ、時間の経過を表現する
こうした構成は、“静”と“動”の対比をもたらします。
満開の華やかさよりも、
その後に残る「余白」にこそ、深い感情が宿る――
それがいけばなにおける「命のリレーの美学」です。
文学と信仰に見る「種」の意味
日本の古典文学にも、「種」を象徴的に詠んだ表現が多くあります。
和歌では「花の種=心の種」として使われ、
『古今和歌集』では“花が咲くのは心の種が育った証”とされました。
また、仏教では「因果の種」という思想があり、
善い行い(善因)は善い結果(善果)を生むと説かれています。
花の命を次へつなぐ“種”は、
人の生き方を映す比喩として、日本文化全体に息づいているのです。
季節ごとの「実」から感じる物語
春 ― 芽吹きの約束
梅の実や木の芽は、春のはじまりを告げるサイン。
花が咲く前にその命を感じさせる存在です。
いけばなに取り入れると、“これからの希望”を表現できます。
夏 ― 豊かに実る時間
青い実や若い果実が、勢いよく成長する季節。
まだ色づく前の瑞々しい実は、生命の充実を象徴します。
ガクアジサイの実やヤマモモの実などが好相性です。
秋 ― 成熟と収穫のとき
赤く熟した実が豊かに色づく秋。
南天、柿、木の実、穂を抱いた稲――どれも自然からの贈り物。
実りの季節はいけばなでも“感謝”を込める時間です。
冬 ― 静けさの中の生命
冬に残る実は、雪の中で小さな灯りのように輝きます。
南天やヒイラギの実、松ぼっくりは、
“命の残響”として空間にぬくもりを与えます。
暮らしの中で「命の循環」を楽しむ
私たちの暮らしの中でも、“花の命がめぐる”瞬間に気づくことがあります。
散った花びらをそのまま飾ってみたり、
ドライにして種や実をリースに使ったり――
それは「命の余白」を愛でる行為です。
いけばなを通して、ただ花を飾るのではなく、
花が生きた時間の“つづき”を表現する。
そこに、日本人が大切にしてきた「自然とともに生きる心」が息づいています。
Q&A|種と実をいけるときの工夫
Q. 種や実をいけるとき、どんな花器が合いますか?
A. 種や実は落ち着いた色合いなので、器も“静”を感じる素材が合います。 陶器や素焼きの花器、木目の花台など、自然素材を選ぶと一体感が生まれます。 一方で、ガラスの花器にドライの実を入れると、光を透かして“時間の透明感”を表現できます。
Q. 実が落ちやすい枝を長持ちさせるには?
A. 切り口を斜めに切り直し、ぬるま湯につけて水揚げを良くします。 また、実の部分に直接霧吹きすると傷みやすいので、枝葉を中心に湿度を与えるのがコツです。 乾燥が気になるときは、ドライ用のスプレーや植物オイルでコーティングしても長持ちします。
Q. 種や実を“飾るだけ”でも意味はありますか?
A. もちろんあります。 いけばなは「生ける行為」そのものが心の表現ですが、 飾るだけでも“命の名残を見つめる時間”として十分に価値があります。 小皿やガラスボウルに季節の実を数粒並べるだけで、部屋に穏やかな季節の気配が漂います。
まとめ|花の終わりは、次の始まり
種も実も、花の“あと”に生まれる存在です。
けれど、それは終わりではなく、次の命への橋渡し。
いけばなにおいても、
咲き誇る花だけでなく「その後の命」を見つめる視点こそが、
日本の美意識をより深く映し出してくれます。
花が終わったあとにこそ見える“静かな美”。
それを感じ取れる心が、いけばなの本質なのかもしれません。